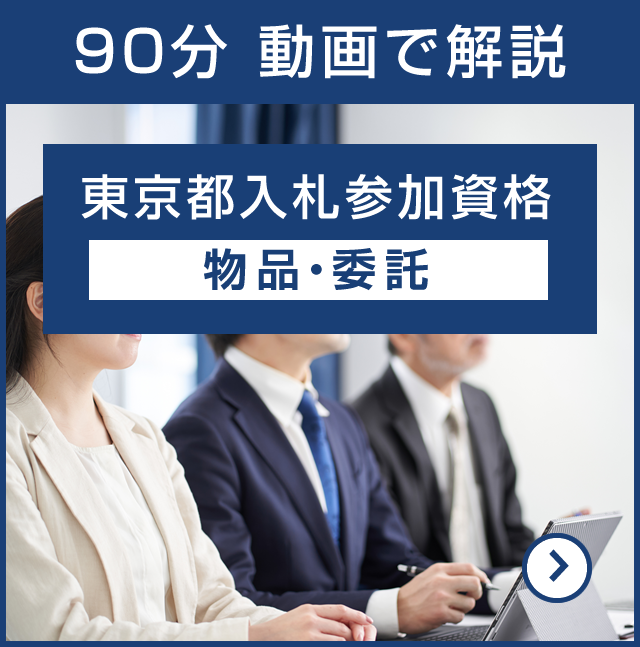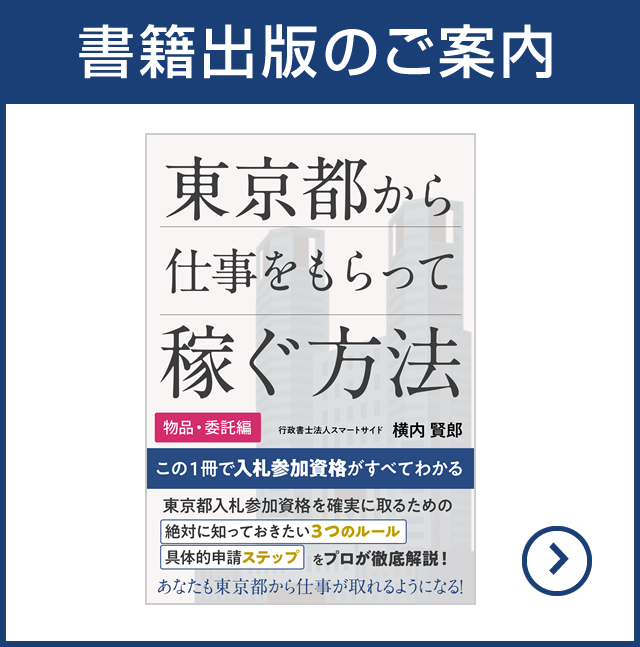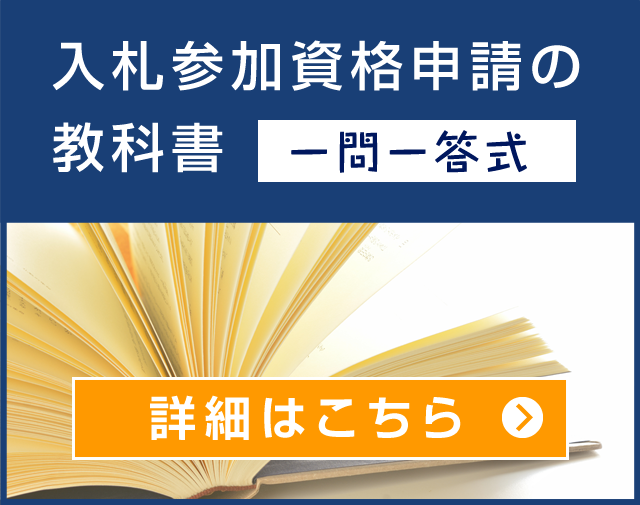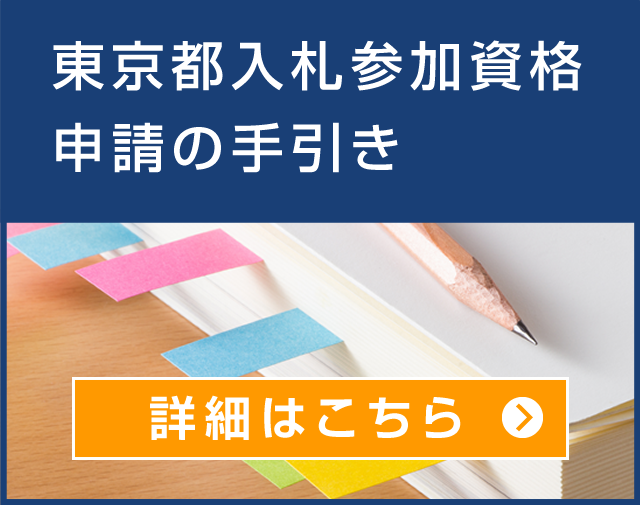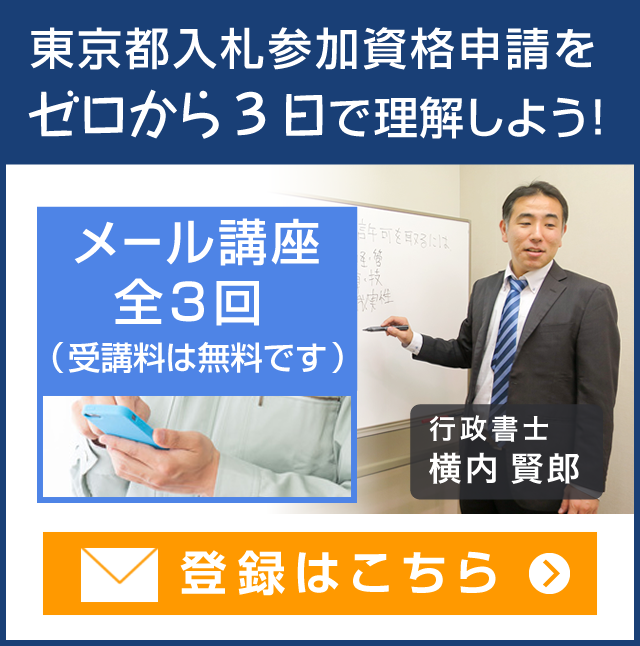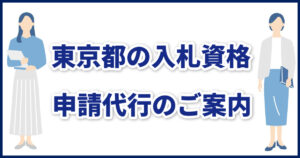
皆さんの中には「東京都入札参加資格を申請したいけどやり方がわからない…」とか「東京都の入札に参加したいけど、はじめるにはどうすればよいのかわからない?」といったように、
■ 東京都電子調達システムの事前準備
■ 東京都入札参加資格の電子申請
■ 入札参加資格を取得するための東京都の手続き
について、お困りの方はいらっしゃいませんでしょうか?「東京都入札参加資格申請」といったワードでネット検索をしてみても、
- 東京都のホームページのどこをみれば良いのか?
- 申請の手引きはどこに載っているのか?
- 東京都に聞くにしても、どこに電話すればよいのか?
というように、わからないことだらけで、入札参加資格を申請するためには「何」から準備すればよいのか、まったく先に進むことができないという方も少なくないのかもしれません。
行政書士法人スマートサイドは、東京都入札参加資格取得のための代行手続きを大変得意とした行政書士事務所です。いままで数多くの事業者さまの、東京都入札参加資格の取得手続きを代行し、公共事業の案件落札をサポートしてきました。このページでは、上記のような、お困りごとを抱えている皆さんのために、東京都入札参加資格申請の専門家である行政書士法人スマートサイドが「まったく初めての人でも、情報迷子にならないように」東京都の入札参加資格の取得について、わかりやすく解説しています。

東京都の入札参加資格申請に精通した行政書士。これまで多くの建設会社・物品販売業者・委託業者の入札参加資格取得を支援し、急ぎの案件や地方の会社からの依頼に対して、数多く対応してきた実績を持つ。豊富な経験に基づく正確な手続きには定評があり「東京都入札参加資格の専門家」として高い信頼を得ている。「入札参加資格申請は事前知識が9割」を出版。インタビューは、こちら。
- 入札って、「誰でも」できるのではないの?
- 入札って、「いつでも」できるのではないの?
- うちの会社に東京都の入札参加資格なんてあるの?
- 確か、以前、入札に参加したことあるはずだけど?
- 全省庁の入札資格なら持っているけど、それじゃダメなの?
といったように、東京都の入札参加資格に関する基礎知識がないと、さまざまな疑問にぶつかってしまいます。そこで、まずは、東京都入札参加資格という言葉を初めて聞く人にも分かるように、「申請の手続きの流れ」「申請に係る費用」の説明の前に「東京都入札参加資格(物品・委託)の概要」について、説明させて頂きます。
東京都の入札に参加するには?
東京都の入札に参加するには、東京都の入札参加資格を持っていなければなりません。東京都の入札参加資格を持っていないのに、東京都の入札に参加することはできないんです。たとえば、「埼玉県の入札資格ならある」「神奈川県の入札になら参加している」「省や庁の入札に参加するための全省庁統一資格ならある」といったとしても、やはり、東京都の入札に参加するには、東京都の入札参加資格が必要です。
東京都の入札参加資格を持つには、東京都が定めるルールに則って入札参加資格の申請をしたうえで、東京都から承認を得なければなりません。
今すぐ東京都の入札に参加したい…?
「いますぐ、東京都の入札に参加して案件を落札したい…」「来月の入札に間に合うように資格を取得したい…」といったように、急いでいる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、どんなに急いで入札に参加したくても、入札参加資格を取得しなければ、東京都の入札に参加することはできません。おおよそのスケジュールですが東京都の物品委託の場合、毎月10日ころまでに申請をすると、翌月1日から資格適用になります。そのため、たとえば、20日に東京都に申請をしたとしても、翌月1日からの資格適用にはならず、翌々月の1日からの資格適用になります。
このように申請の準備をして、申請をして、資格を取得して、入札に参加できるようになるには、およそ1~2か月程度の期間が必要になります(物品・委託の場合)。
「誰でも簡単に取得できる…」というのは大間違い
東京都のホームページにある手引きを見たり、ネット検索して申請の仕方を見て、途方に暮れてしまった方も多いのではないでしょうか?素人の方が、自力で、東京都の入札参加資格を短期間で不備なく取得するのは、非常に難しいと言えます。
- いつまでに申請するといつから入札に参加できるのか?
- 申請のために必要な書類は何なのか?
- 事前に準備するものは何なのか?
- 電子申請をどうやってやるのか?
みなさんも同じようなことでお悩みなのかもしれませんが、「人に聞きながらやればわかる」とか「自分で調べながらやればできる」とうレベルの作業ではないような気がします。
有効期間は最大で2年間
東京都の入札参加資格の有効期間は最大で2年です。「令和〇年度と令和〇年度」の資格といったように、2年度ごとの期間を設けて、入札参加資格の有効期間が設定されています。正確には、令和〇年4月1日から翌々年の3月31日までが、資格の有効期間ということになりますね。
このように2年ごとの更新手続きが必要なため、少しでも早く東京都の入札資格を取得した方が、より長く入札に参加できる(資格を維持できる)ようになっています。そのため、思い立ったが吉日で、なるべく早く入札参加申請をして、入札参加資格を取得した方が、落札の機会が高まるという関係性にあります。
電子証明書の取得・パソコンの環境設定が必要
電子証明書の取得・パソコンの環境設定が必要であるということについては、東京都に入札参加資格を申請する際の、最大の特徴といっても過言ではありません。他の県の場合、入札参加資格を取得した後に、パソコンの環境設定を行わなければならないことがほとんどです。しかし、東京都の場合は、「入札参加資格を取得する前」に「入札参加資格の申請をする事前準備」として電子証明書の取得・パソコンの環境設定が必要になります。
皆さんの中に、「都庁に書類を提出しさえすれば、入札資格を取得できる」と勘違いしていた方もいらっしゃるかもしれませんね。東京都の入札資格を取得するには「電子証明書の購入・パソコンの環境設定」から始めなければなりません。電子申請をするための事前準備が必要になります。
そこで、以下では
- 電子申請のためのパソコンの環境設定を中心とした事前準備編
- 事前準備完了後の電子申請を中心とした申請手続編
の2段階に分けて、説明させて頂きます。
【事前準備編】
東京都の入札参加資格を申請するには、以下の事前準備が必ず必要です。この事前準備をいかにスムーズに終わらせることができるか?によって、東京都の入札に参加できる時期が大きく変わってきます。
ステップ1:電子証明書+ICカードリーダの購入
電子証明書とICカードリーダを御社の備品として購入する必要があります。電子証明書とICカードリーダは、電子入札に対応したものを購入する必要があるため、「電子認証コアシステム対応の民間認証局」が発行している「電子入札用の電子証明書とICカードリーダ」が必要になります。
ステップ2:PIN(暗証番号)の受領
「電子入札コアシステム対応の民間認証局」に電子証明書の発行を申し込むと、電子証明書+ICカードリーダの他に、電子証明書を使用するための暗証番号(PIN)が発行されます。この暗証番号(PIN)は、本人限定受取郵便で、電子証明書の名義人宛(通常は、会社の代表取締役のご自宅)に郵送されます。
ステップ3:パソコンの設定
電子証明書・ICカードリーダ・PINの通知の3点が揃ったら、電子証明書を利用するためのパソコンの環境設定が必要になります。各種ソフトのインストール、東京都電子調達システムの事前設定を行います。
ステップ4:電子証明書の登録
パソコンの環境設定が整ったら、電子証明書を使用して東京都電子調達システムに自社情報を登録する必要があります。以降の電子申請を行政書士に委任する場合には、パソコン上で行政書士への委任手続きを行うことができます。
【申請手続編】
電子証明書の取得やパソコンの設定など、事前準備が終わったら、申請手続き(電子申請)を行います。東京都電子調達システムといったシステムにログインして、1つ1つ申請事項を入力していかなければなりません。間違いのないように、手引きの読み込み、マニュアルの確認が必須です。
ステップ1:電子申請
東京都電子調達システムを利用して、申請営業種目、売上高、過去の契約実績、従業員の人数など電子申請を行います。営業種目・取扱品目は、一覧の中から、自社が東京都の入札に参加したいものを選択することになります。最大10営業種目、1営業種目につき8取扱品目まで選択することができます。
売上高については、前期の損益計算書の中にある売上高を、選択した営業種目・取扱品目ごとに割り振らなければなりません。過去の契約実績については、過去3年間の営業種目ごとの「東京都との契約実績」「東京都以外の官公庁との契約実績」を、日付、件名、期間、金額などの詳細にわたって入力する必要があります。
ステップ2:書類の電子送付
電子申請が終わった後に、都庁財務局経理部あてに登記簿謄本などの書類を電子送付します。以前は、郵送していましたが、現在は東京都電子調達システム上に添付して送信します。おおむね毎月10日までに電子申請+必要書類の電子送付を終らせれば、翌月1日から、東京都の入札参加資格を取得できるといったスケジュールになります。「電子申請が完了すれば終わり」ではなく「電子申請完了後に必要書類の電子送付までが必要」になりますので、「履歴事項全部証明書」「貸借対照表、損益計算書、個別注記表」などといった必要書類の送付まで、忘れないように行いましょう。
ステップ3:承認・否承認の通知の受領
申請に不備がなければ、承認通知のメールが届きます。否承認となった場合には、補正・訂正が必要です。
ステップ4:資格適用・有資格者名簿への登載
承認通知が届いた翌月、もしくは翌々月から入札資格の有資格者名簿に登録され、東京都の入札に参加することができるようになります。
以下では
- 東京都入札参加資格申請のための手続きの流れが理解できない
- 手続きの流れを理解したとしても自分でできそうにない
- 面倒なことは専門家にお任せしたい
- 東京都の入札資格の申請を丸ごと代行してほしい
といった方たちに向けて、東京都入札参加資格の申請を行政書士法人スマートサイドにご依頼頂いた際のメリットについて、詳しく、ご紹介させて頂きます。
メリット1:御社に代わって電子証明書の購入および受取代行
東京都の入札参加資格を申請する上において、何にもまして、面倒なのが、「電子証明書の取得・ICカードリーダの取得」です。手続きの流れでも説明したように「電子証明書+ICカードリーダ」を事前に準備しなければ、東京都の入札参加資格を申請することができません。
電子証明書やICカードリーダは、
- 電子証明書の購入申込書類を作成の上、
- カード名義人の住民票や印鑑証明書とともに
- 電子入札コアシステム対応の民間認証局へ郵送
しなければ購入することができません。また、電子証明書は「本人限定受取郵便」で発送されるため、カード名義人(通常は代表取締役)本人が、最寄りの郵便局まで受け取りに行かなければなりません。東京都入札参加資格の申請を行政書士法人スマートサイドにご依頼頂いた際には、電子申請を行う前に必要な事前準備であるこれらの煩わしい手続きのすべてを御社に代わって代行することが可能です。
■ 電子証明書購入申し込み書類の作成
■ 購入の申込の手続き代行
■ 電子証明書+ICカードリーダの受領
までの一連の手続きを御社に代わって、弊所にて代行いたします。
メリット2:御社に伺って、パソコンの環境設定
当然ですが、電子証明書やICカードリーダを購入しただけでは、東京都の入札参加資格を電子申請することはできません。電子証明書やICカードリーダを利用できるようにするために
- 各種ソフトのインストール作業
- 東京都電子調達システムを利用できるよにする環境設定
の2つが必須になります。パソコンの操作に慣れているシステム担当やセキュリティ担当がいれば、よいかもしれませんが、パソコン操作の苦手な人にとっては、とても難しくイライラする作業になることでしょう。
行政書士法人スマートサイドでは、電子入札に必要なパソコンの環境設定、動作確認のすべてを実際に御社まで伺って、御社のパソコンにて行います。パソコンの操作が苦手な人でも、操作マニュアルを読んだり、ヘルプデスクに問い合わせをすることなく、電子入札に必要なパソコン環境を手に入れることができます。
メリット3:御社に代わって、電子申請
- 申請に必要な事項(売上高や営業種目など)
- 申請に必要な書類(登記簿謄本や財務諸表など)
は、すべて手引きに細かく記載されています。手引きを隅から隅まで十分に注意しながら読み込めば、自分で申請できるかもしれません。しかし、「そこまで時間がない」「労力をかけたくない」といった人がほとんどではないでしょうか?あげくの果てに、自分でやってしまったがために申請内容が間違っていたとなってしまっては、すべての苦労が水の泡になってしまいます。
申請に必要な事項の入力、送信、必要書類の郵送は、すべて東京都入札参加資格申請のプロである行政書士法人スマートサイドで行います。御社は、弊所からメールする簡単なヒアリングにご回答いただくだけです。手引きの細かい部分の読み込みや、申請のための一切の作業は、不要になります。
メリット4:承認通知から資格適用までスケジュール管理
- いつまで申請すれば、いつから入札に参加できるか?
- 取得した資格は、いつまで有効なのか?
- 次回はいつ、都庁へ入札参加資格を申請しなければならないのか?
といったスケジュールについては、とても気になるところですね。弊所にご依頼頂いた際には「申請後の承認・否承認の通知の確認」「資格適用までのスケジュール確認」のすべてを、弊所で行います。御社は資格が適用されるまで、何もすることなく、結果通知書が発行されるのを待つだけです。
事前相談料(要予約)
ご希望のお客様にのみ、事前相談(1時間程度)を実施いたします。場所は、弊所です。
| 事前相談料(1時間) | 11,000円(税込み) |
|---|
※相談日前日までに、指定の口座に相談料をお振込み頂きます。
電子証明書+ICカードリーダの代行取得費用
東京都の入札参加資格を取得するために必要な電子証明書とICカードリーダを御社に代わって取得します。
| 電子証明書の代行取得費用 | 55,000円(税込み) |
|---|
※別途、履歴事項全部証明書の取得費用を1通につき2,200円ご請求させて頂きます。
パソコンの訪問設定費用(※都内のみ)
御社に伺って、入札に必要なパソコンの環境設定、電子証明書の動作確認を行います。
| パソコンの訪問設定(都内のみ) | 33,000円(税込み) |
|---|
※東京都以外への訪問設定をご希望の場合、別途、出張料(22,000円)をご請求させて頂きます。
東京都への入札参加資格申請の代行費用
弊所のパソコンを使って、御社に代わって、東京都への入札参加資格の電子申請および必要書類の郵送を行います。申請営業種目の数に応じて、価格を設定しています。
| 申請営業種目が1~4業種の場合 | 110,000円(税込み) |
|---|---|
| 申請営業種目が5~7業種の場合 | 143,000円(税込み) |
| 申請営業種目が8~10業種の場合 | 176,000円(税込み) |
※申請営業種目は、最大で10個まで選択することができます。
費用に関する注意事項
- 事前相談は、有料の予約制になっています。
- 法定必要書類については、1通あたり2,200円の取得費用(実費分込み)をご請求させて頂きます。
- 正式にご依頼を頂き次第、請求書を発行いたします。請求書発行後、5営業日以内に指定の口座にお振込みください。
- 電子証明書とICカードリーダの本体価格(約5万円程度)は、上記のお見積りの中に含まれておりません。
- 電子証明書とICカードリーダの本体価格は、別途、購入元の民間認証局から発行される請求書に従い、御社から直接、購入元にお振込み頂くことになります。
- 東京都入札参加資格の申請
- 東京都の入札に参加するための手続き
- 電子入札のための東京都への入札参加申請
を行政書士法人スマートサイドに依頼してみようと思って頂いた方もいるかもしれませんね。
弊所では「電話でのお問合せ」ではなく「問い合わせフォームからのご依頼」をお願いしています。というのも、電話で、口頭でやりとりすると「メモ(文章)が残らない」「聞き間違い、言い間違い、勘違いが生じやすい」といったことから、入札参加資格を申請するうえでの致命的なミスが起こりかねません。例えば「申請先を間違える」「申請する営業種目や取扱品目を間違える」「売上高の割り振りや従業員の人数といった入力事項を間違える」といった取り返しのつかないミスが発生する可能性が高いからです。
手続きや申請についての相談は、別途、有料の事前予約制で受け付けておりますので、ご依頼の際は、下記問い合わせフォームから送信して頂くようにお願いいたします。
手順1:問い合わせフォームから送信
行政書士法人スマートサイドでは、電話でのご依頼は承っておりません。東京都の入札参加資格を取得したい方は、ホームページ上にある「問い合わせフォーム」からご連絡下さい。電話連絡による「言い間違い」「聞き間違い」「勘違い」を防ぎ、業務の効率性を高める観点から、電話での依頼・質問・確認は、ご遠慮いただいておりますので、あらかじめご了承ください。
![]()
手順2:打ち合わせ・相談日時の調整
お問合せフォームからのメールが届き次第、打ち合わせ・相談日時を調整のうえ、ご登録いただいたメールアドレス宛に返信させて頂きます。弊所とのやり取りは、原則としてメールでのやり取りになります。なお、「事前相談なしでのご依頼・お申込み」も受け付けておりますので、その際は、相談料(11,000円・税込み)は、発生しません。
![]()
手順3:相談料のお振込み
打ち合わせ・相談日時が決定次第、相談料(11,000円・税込み)の請求書をメールにて送信いたします。相談日前日までに、指定の口座にお振込みをお願いいたします。
![]()
手順4:打ち合わせ・相談の実施
弊所にて、1時間程度の打ち合わせを行います。「どのような営業種目で入札に参加したいのか?」「東京都、区市町村、全省庁のいずれの入札に参加したいのか?」「いつから入札に参加したいのか?」「電子証明書の購入の準備は、どのように行うのか?」「入札に参加できるようになるまで、どれくらいの期間が必要か?」といった点について、詳細にご説明させて頂きます。
![]()
手順5:正式なご依頼/申請代行費用のお振込み
打ち合わせを経て、正式に弊所にご依頼いただけるとなれば、申請代行費用の請求書を発行いたします。申請代行費用は、請求書発行後5営業日以内に指定の口座にお振込みください。
![]()
手順6:東京都入札参加資格申請手続きの開始
入金の確認が取れ次第、東京都入札参加資格の申請に関する手続きを開始させて頂きます。手続きの流れの箇所で説明した「事前準備」と「申請手続」を経て、およそ1~2か月後には、東京都の入札に参加できるようになります。
最後に…
行政書士法人スマートサイドは、東京都入札参加資格申請の専門家として、今までたくさんの会社の申請代行を行ってきました。過去には、資格取得の半年後に9億円の案件を落札した会社もいらっしゃいます。また、東京都だけでなく、全省庁統一資格、神奈川県、埼玉県の入札参加資格を代行申請することも可能です。
突然ですが、皆さんの目標は何ですか?皆さんの目標は、あくまでも「入札案件を落札し、売上高をアップさせること」にあるはずです。そうであるならば、その前段階である入札参加資格の取得に、時間と労力をかけている場合ではありません。
- 入札に参加するための資格の取得方法がわからない
- 入札参加資格を取得するのに時間がかかってしまった
- ヘルプデスクに何度も電話して聞いたけど、理解できない
- 手引きやマニュアルを読んでも、申請できなかった
ということでは、同業や競合他社に大きな遅れを取ってしまいます。そんな時こそ、行政書士法人スマートサイドにご依頼ください。行政書士法人スマートサイドでは、
■ 電子証明書+ICカードリーダの申込・取得
■ パソコンの設定
■ 東京都電子調達システムからの電子申請
■ 申請後の進捗状況の管理
といったすべてを代行することが可能です。手続きに関する煩わしさ、ストレスを避けたいのであれば、東京都入札参加資格の取得を行政書士法人スマートサイドに依頼してみませんか?