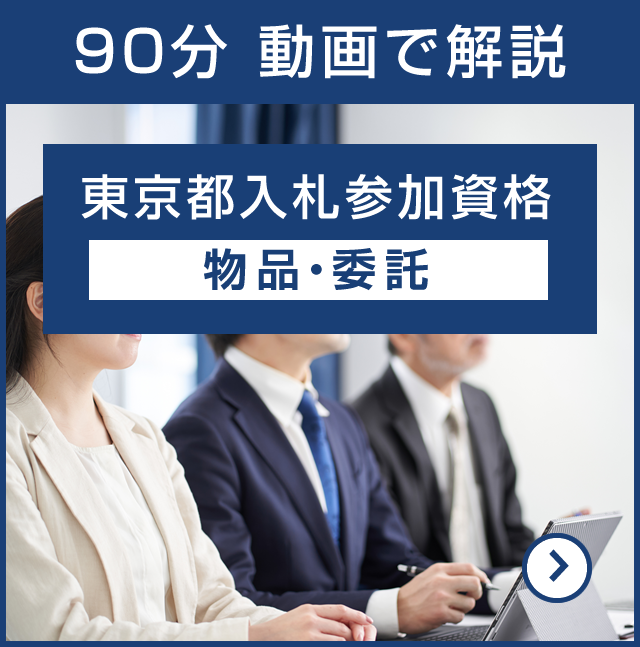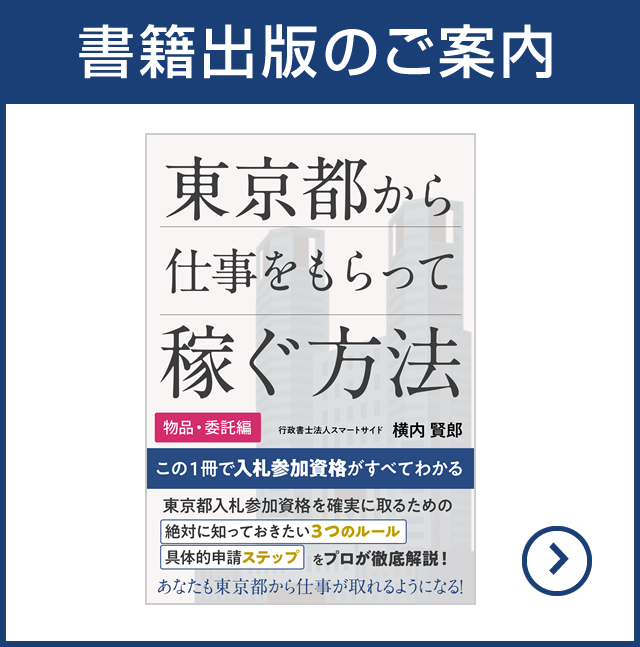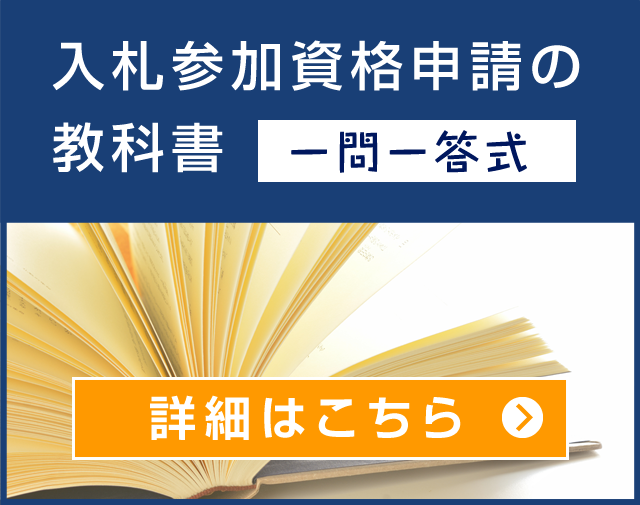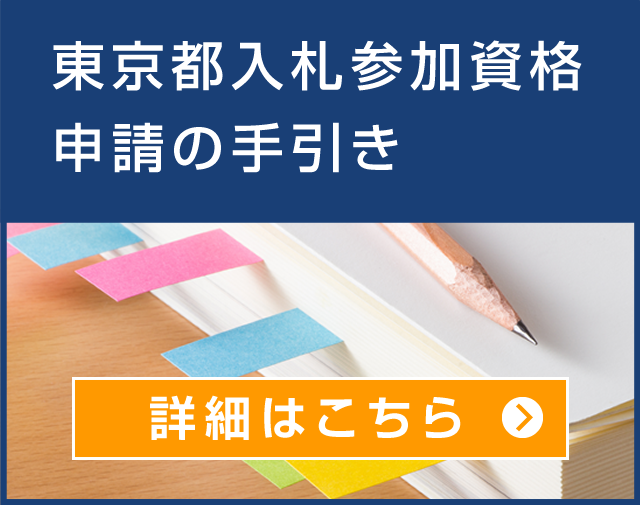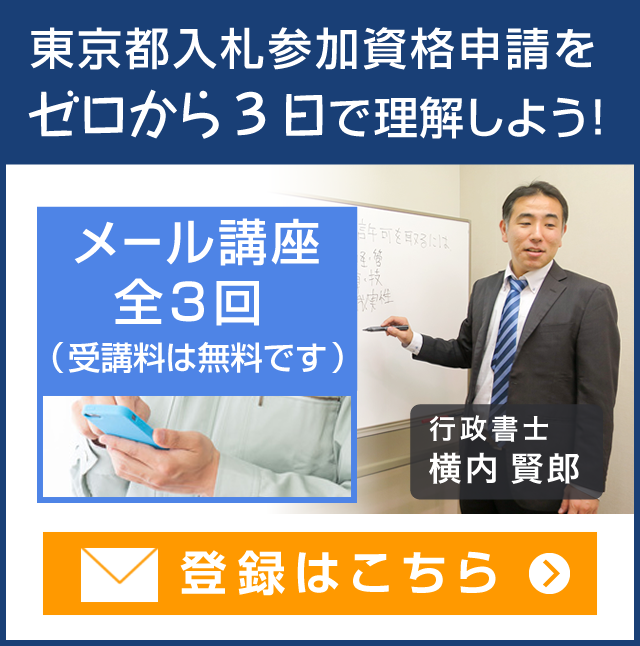■ 役所の人から、入札参加資格を持つように言われている!
■ なぜか自分が、社内の入札資格担当になってしまった!
■ 販路の拡大のため、役所の仕事も引き受けたい!
御社は、どのような理由で、入札参加資格を取得したいとお考えですか?会社の代表者であれば「入札に参加して、役所の仕事も引き受けたい」とお考えの方もいるでしょう。一方で、自分が社内の入札参加資格担当に抜擢され、「何から始めればよいかわからなくて困っている」という方もいるでしょう。また、役所から「入札資格を持っておいてください」とお願いされている事業者も多くいらっしゃいます。入札参加資格を取得する理由はともあれ、一口に入札参加資格を取得するといっても「じゃあ、どうすれば良いの?」といったところが本音ではないでしょうか?
このページでは、そんなみなさんに向けて東京都の入札参加資格申請の専門家である行政書士法人スマートサイドが、東京都の入札参加資格を「急ぎ」で取得する際の4つのポイントについて、解説させていただきます。
・自社ではできそうにない
・難しすぎてわからない
・時間がないので、外部の専門家にお任せしたい
という人がいれば、ぜひ、こちらのページから、行政書士法人スマートサイドまで手続きをご依頼ください。

東京都の入札参加資格申請に精通した行政書士。これまで多くの建設会社・物品販売業者・委託業者の入札参加資格取得を支援し、急ぎの案件や地方の会社からの依頼に対して、数多く対応してきた実績を持つ。豊富な経験に基づく正確な手続きには定評があり「東京都入札参加資格の専門家」として高い信頼を得ている。「入札参加資格申請は事前知識が9割」を出版。 インタビューは、こちら。
東京都入札資格を取得する4つのポイント
では、これから初めて入札にチャレンジしようという人は、何から始めればよいのですしょうか?「なんでもよいから、入札したい…」というのでは、入札参加資格の取得のしようがありません。まずは、以下の4点をご確認下さい。
【ポイント1】どこの入札に参加したいか?
みなさんが、どこの自治体の入札に参加したいのか?によって、入札参加資格を取得する手続きや、入札に関するルールが、全く異なってきます。ですので、まずは、どこの自治体の入札に参加するのか?を決定することが、重要です。例えば、東京都の入札に参加するのであれば、「東京都電子調達システム」への登録が必要です。新宿区や中野区といった区市町村への入札であれば、「東京電子自治体共同運営電子調達サービス」がありますので、東京都とは、別の手続きを行う必要があります。仮に防衛省の入札、参議院の入札といった官庁への入札であれば、「全省庁統一資格」という名前の資格を取得する必要があります。
このように、どこの入札に参加したいのか?によって、手続きが全く変わってきますので、まずは、「東京都」「区市町村」「省庁」といったように、どこの入札参加資格を取得すればよいのか?検討してみてください。
【ポイント2】工事か?物品か?役務か?
もし仮に、御社が公共工事への入札を希望しているならば、建設業の許可を取得したうえで、経営状況分析や経営事項審査といった公共工事の入札参加資格を取得するための特殊な手続きを受けなければなりません。一方で、「物品」や「役務の提供」であれば、上記のような特殊な手続きを受ける必要はありません。もっとも、「物品」や「役務の提供」の入札参加資格を取得する際に、例えば「警備業」「産業廃棄物収集運搬業」のように申請時に営業の許可を取得していなければならない業務もあります。
公共工事への入札を希望しているのか?物品・役務への入札を希望しているのか?によって手続きが全く異なってきます。
【ポイント3】いつまでに入札に参加か?
東京都への入札であれば、2年に1度の定期受付があり、その定期受付に申し込めば、2年間は有効な入札参加資格を持つことができます。一方で、東京都内区市町村には「定期受付」といった申請方法はなく、常に随時受付で申請することになります。さらに、全省庁統一資格であれば、定期受付は3年に1度です。それぞれ、いつ申請すれば、いつから資格が取れるのか?といったスケジュールが大きく異なります。
「いつまでに入札参加資格を取得したいのか?」を決めて頂く必要があります。
【ポイント4】営業種目・取扱品目の決定
例えば、御社の強みが「文房具事務用品・図書」の販売だとしても、「文房具事務用品・図書」という営業種目の中には、さらに「文房具」「用紙類」「封筒」・・・などといったように細かな取扱品目に分かれています。東京都の物品委託の入札資格の場合、最大で10営業種目を選ぶことができます。1営業種目につき8取扱品目を選択することができます。
自分の会社が、どの営業種目やどの取扱品目を選択するかについて、事前に決定しておいて頂く必要があります。
行政書士法人スマートサイドの特徴

行政書士法人スマートサイドは、東京都入札参加資格申請の専門家として、以下のような特徴があります。
・物品/工事の両方の入札参加資格申請に精通しています。
・電子証明書の取得手続きやパソコンの環境設定もサポート可能です。
・承認/否承認の確認、受付票のプリントアウトなど申請後の状況も確認させていただきます。
行政書士法人スマートサイドなら、入札参加資格に関するお客さまのご要望を丁寧にヒアリングし、申請手続きの代行を行うことができます。また、パソコン上で「行政書士への委任手続き」を行うことによって、「必要事項の入力」から「必要書類の郵送」、「承認・非承認の結果確認」まで、一括して管理いたします。そのため、ご自身で手続きを行うよりも御社が負担する作業量は、3分の1以下になります。
サービス一覧
| 電子証明書・ICカードリーダの取得申し込み/受取代行 | 〇 |
| パソコンの設定 | 〇 |
| 必要事項の入力・代理送信 | 〇 |
| 必要書類の収集・郵送 | 〇 |
| 承認・非承認の結果確認 | 〇 |
| 次回更新までのスケジュール管理 | 〇 |
料金表
(相談料)
| 相談料(面談形式:1時間) | 11,000円 |
|---|
(事前準備)
| 電子証明書・ICカードリーダー申請 | 55,000円 |
|---|---|
| パソコンの設定(日当) | 33,000円 |
(申請手続き)
| 工事 | 110,000円~ |
|---|---|
| 物品 | 110,000円~ |
| 全省庁統一資格 | 110,000円~ |
東京都の入札参加資格の取得でお困りなら…

行政書士法人スマートサイドは、東京都入札参加資格の申請手続きの専門家として、いままで多くの会社の入札参加資格を取得してきました。その中には
- 東京都の入札に新規で参入したいと考えていた企業
- 担当者が退職し、手続きの方法がわからななくなっている会社
- 更新時期が迫っているのに、まったく準備が進んでいない担当者
- 申請を外注したいが、どこに頼んでよいかわからない社長
など、さまざまなケースがありました。もし、みなさんが同じような状況で悩んでいるなら、ぜひ、行政書士法人スマートサイドに手続きをご依頼ください。
また、行政書士法人スマートサイドでは、「手続きの不安を解消したい」「事前にスケジュールを共有したい」「疑問点を相談したい」という人のために、1時間11,000円の事前予約制の有料相談を実施しています。「まずは、相談を…」と思っている人にとって、とても好評を頂いているサービスです。
事前予約制の有料相談では
■ 東京都電子調達システムの設定方法
■ 等級や格付けの基準
■ 電子証明書+ICカードリーダの取得方法
■ 申請の際のチェックポイント
など、御社のご要望に応じて、手引きを見ただけでは、なかなか理解することが難しい情報を提供させていただくことも可能です。ぜひ、事前予約制の有料相談もご活用ください。
それでは、みなさんからのご連絡をお待ちしております。