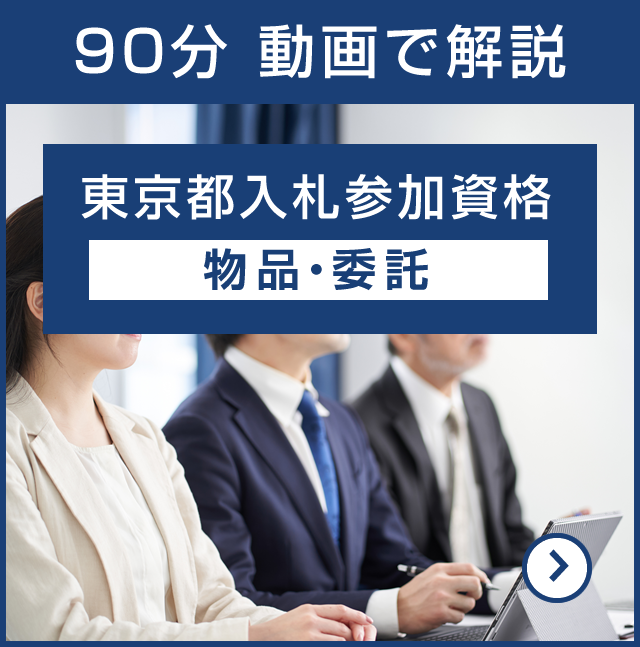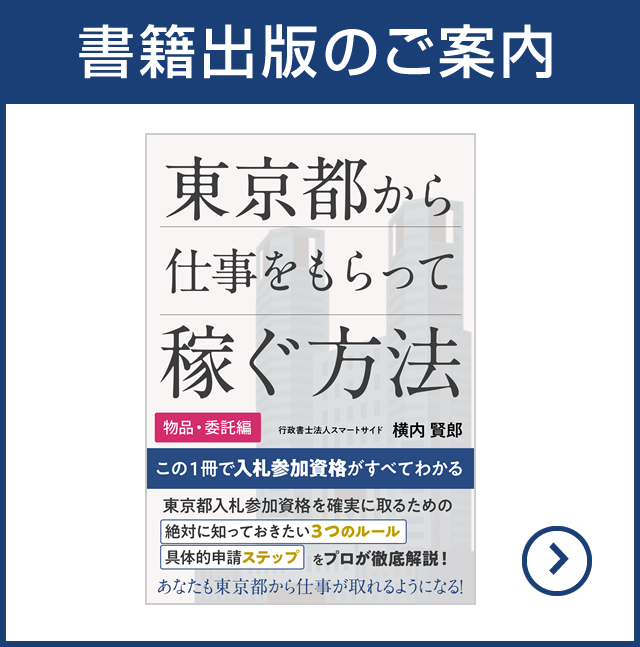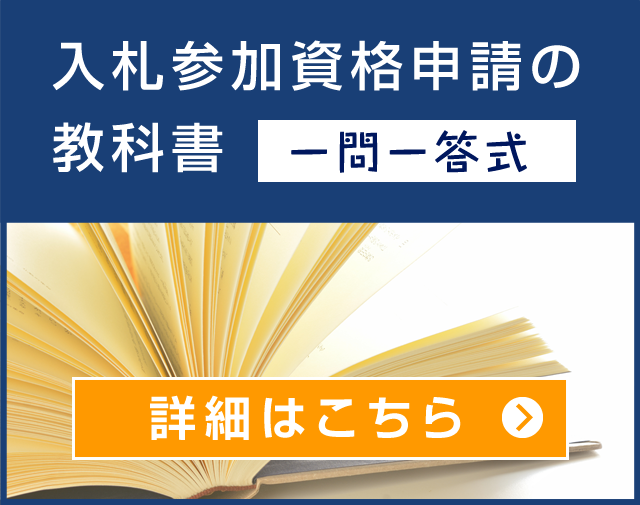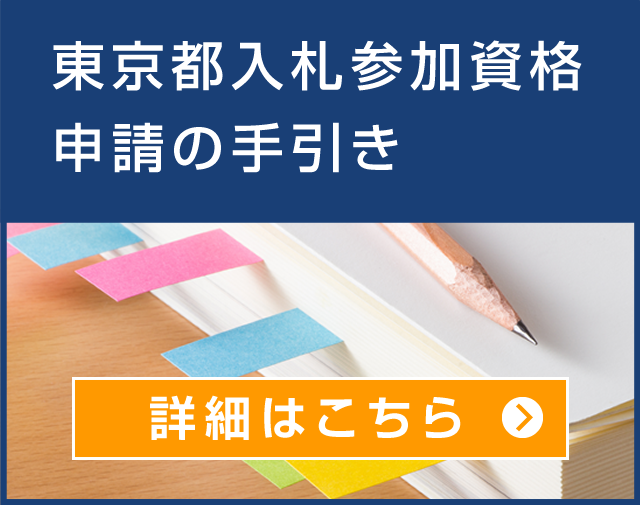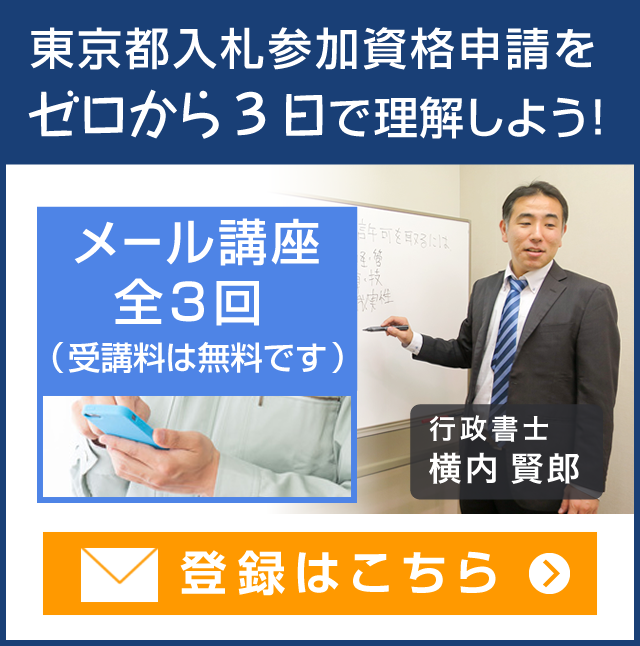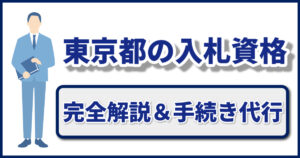

東京都の入札参加資格申請に精通した行政書士。これまで多くの建設会社・物品販売業者・委託業者の入札参加資格取得を支援し、急ぎの案件や地方の会社からの依頼に対して、数多く対応してきた実績を持つ。豊富な経験に基づく正確な手続きには定評があり「東京都入札参加資格の専門家」として高い信頼を得ている。「入札参加資格申請は事前知識が9割」を出版。 インタビューは、こちら。
このページは、東京都の入札サポートの専門家である行政書士法人スマートサイドが、「東京都の入札」について、初心者の方のために、全体像をわかりやすくご説明するために記載したページです。
 |
東京都の入札に参加したいが手続きが全くわからない…
私自身が「はじめて」なうえに、社内にできる人もいないので、どうにもならない。だれかできる人がいたら、すぐにでもお願いしたい。 |
|---|
 |
都庁のホームページを見たけれど、難しすぎる…
なんとなく東京都のサイトを見てみたけれど、難しいどころか、どこに何が書いてあるのかすら、よくわからない状態で、先に進める気がしない。 |
|---|
 |
時間ができたらやろうと思っていたけど…
「やろう、やろう」と思っていたけど、本業が忙しすぎて資格の取得に割く時間がない。あっというまに半年以上が立ってしまって、まったく進んでいない。 |
|---|
(こんなお悩みありませんか?)
■ 東京都の入札に参加したいが手続きが全くわからない
■ 都庁のサイトを見ても、難しくて理解できない
■ 自社で電子申請をはじめたいが、うまくできるか不安
■ 本業が忙しすぎて資格の取得に割く時間がない
ということで困ってしまっている人はいらっしゃいませんでしょうか?もしくは、社内会議の結果、東京都の入札に積極的に参加して行こうという方向性が決まったものの、どういった手続きを何からしていけば良いか分からなず、ネットで情報を収集しているという人もいるのではないでしょうか?このページは、そんなみなさんのために記載していきます。これから東京都の入札について、検討している人は、ぜひ、このページを参考に、より申請手続きや入札参加資格について、理解を深めてください。
まず、東京都の入札は、誰でも自由にいつでも参加できるわけではありません。東京都の入札に参加するには、東京都の入札参加資格という資格を取得しなければなりません。
逆の言い方をすると、東京都の入札参加資格を持っていなければ、東京都の入札には参加することができないのです。たとえば、実際に東京都から発注されている案件を見てみると、下記のような発注情報がありました。これは、実際に公表されている案件の概要を簡略化したものです。
| 件名 | USBメモリ型ウイルス対策ツールの買入れ | ||
|---|---|---|---|
| 営業種目 | 002:事務機器・情報処理用機器 | ||
| 発注等級 | C | ||
| 受付等級 | C | ||
| 申請要件 | 東京都における令和〇・〇年度物品買入れ等競争入札参加資格を有し、営業種目002「事務機器・情報処理用機器」の「C」に格付けされていること | ||
上記のうち「申請要件」の前半部分、「東京都における令和〇・〇年度物品買入れ等競争入札参加資格を有し」とあるように、この入札案件に参加するには、令和〇・〇年度の東京都の入札参加資格を持っていなければならないのです。このように東京都の入札には、「誰でも」「いつでも」「自由に」参加できるわけではなく、東京都の入札参加資格を持っていなければ、参加できないという点に注意をしてください。
それでは、東京都内の区市町村(新宿区・渋谷区・江東区・小平市・三鷹市など)の入札参加資格を持っている場合や、国の機関である防衛省や財務省の入札参加資格を持っている場合、東京都の入札には参加できるのでしょうか?
この場合、新宿区や渋谷区といった区市町村は東京都内にあります。また、防衛省や財務省の本省は都内にあります。しかし、東京都内の区市町村および国の機関である省庁と、東京都とでは、入札に関するシステムやルールが全く別物であるため、たとえ、区や市や省庁の入札参加資格を持っていたとしても、東京都の入札に参加するには、東京都の入札参加資格を取得する必要があります。
それでは、東京都の入札といっても、どんな種類があるのでしょうか?どういった業務分野の入札案件があるのか?という点についての説明です。まず、東京都の入札資格は以下のように「建設工事等競争入札参加資格」と「物品買入れ等競争入札参加資格」の2つに分けることができます。
「建設工事等競争入札参加資格」の中には「公共工事」のほか「建築設計・土木設計・設備設計」の設計、「測量・地質調査」が含まれています。「物品買入れ等競争入札参加資格」の中には「物品」「委託等」が含まれています。
| 東京都競争入札参加資格 | |||
|---|---|---|---|
| 建設工事等競争入札参加資格 | 物品買入れ等競争入札参加資格 | ||
| 建設工事 |
建築設計 土木設計 設備設計 測量 地質調査 |
物品 | 委託等 |
まず、「建設工事等競争入札参加資格」については、比較的わかりやすいかと思います。いわゆる公共工事に該当するものが、「建設工事等競争入札参加資格」の中に含まれます。そのため、これから公共工事の入札にチャレンジして行きたいという建設会社の人は、東京都の「建設工事等競争入札参加資格」を取得する必要があります。また、各種の設計や測量・地質調査も「建設工事等競争入札参加資格」に含まれますので、設計会社や測量会社で東京都の入札に参加したいという人は、同じく「建設工事等競争入札参加資格」を取得する必要があります。
続いて「物品買入れ等競争入札参加資格」については、名称が「物品買入れ等」となっていますが「物品」のほかに「委託等」も含まれています。「物品」の中には、「文房具事務用品」「事務機器」「学校教材」「繊維・ゴム製品」「室内装飾品」「家電・カメラ」「産業用機械器具類」「通信用機械器具類」「医薬品」「防災用品」といった営業種目があります。「委託等」の中には「印刷」「建物清掃」「警備」「通信施設保守」「道路・公園管理」「害虫駆除」「運送等」「広告代理」「映像等製作」「情報処理業務」「労働者派遣」「事務支援」といった営業種目があります。
東京都の入札参加資格を持つと、どの機関の入札に参加することができるようになるのでしょうか?当然のことながら、東京都の入札参加資格ですから、埼玉県や大阪府の入札に参加することはできません。また、前述した通り、「都内区市町村の入札や省庁の入札」と「東京都の入札」は全くの別物ですから、東京都の入札資格を持っていたからと言って、新宿区や渋谷区といった区市町村および省庁の入札に参加することはできません。
以下では、東京都の入札参加資格を取得した場合に、入札に参加できる東京都の機関を一覧にしてまとめましたので、参考にしてみてください。
| 財務局 | 交通局 | 水道局 | 下水道局 |
| 政策企画局 | デジタルサービス局 | 総務局 | 主税局 |
| 生活文化スポーツ局 | 都市整備局 | 住宅政策本部 | 環境局 |
| 福祉保健局 | 産業労働局 | 中央卸売市場 | 建設局 |
| 港湾局 | 会計管理局 | 子供政策連携室 | 東京消防庁 |
| 教育庁 | 選挙管理委員会 | 人事委員会事務局 | 監査事務局 |
| 警視庁 | 労働員会事務局 | 収用委員会事務局 | 議会局 |
これから、東京都の入札に参加しようとしている人は、どの機関の入札に参加するのか?という点についても、確認をしてみてください。例えば、「東京消防庁」や「警視庁」は「庁」という名称がつくものの、全省庁統一資格ではなく、東京都の入札参加資格の対象になっています。
東京都の入札サポートをしている弊所には、「これから急ぎで手続きをした場合、いつから、東京都の入札に参加できますか?」という質問がよくあります。
東京都の入札に参加するには、東京都の入札参加資格を取得しなければならないわけですが、東京都の入札参加資格の取得スケジュールは以下の通り、おおむね毎月10日までに申請すると翌月の1日から資格適用(東京都の入札に参加できる)となっています。
| 申請受付期限 | おおむね毎月10日までに申請が必要 | ||
|---|---|---|---|
| 適用開始日 | 不備がなければ翌月1日から資格適用 |
このスケジュールは東京都が設定している入札参加資格の受付スケジュールであるため、これ以上、早くすることはできません。例えば、「来週の入札に間に合わせるために急いで欲しい」「入札期限が5日後なので、それまでに何とか資格を取得したい」という希望があったとしても、上記のスケジュールにある通り、東京都の入札に参加できるのは、どんなに早くても翌月1日からになります。
東京都から入札案件が公表されると「いついつまでに希望申請を提出してください」という希望申請期間が定められています。この希望申請の期限は、入札案件が公表されてから1週間程度に設定されていることが多いようです。希望申請の提出は、東京都電子調達システムを通じて、東京都入札参加資格を持っていることを前提にしていますから、案件の公表時点で入札参加資格を持っていなければ、公表された案件に入札することは不可能ということになります。
(案件ごとの公表日と希望申請期間)
| 公表日 | 件名 | 営業種目 | 希望申請期間 |
|---|---|---|---|
| 11/6 | 電子掲示板の買入れ | 産業用機械器具類 | 11/20~11/27 |
| 11/20 | 学習ノート印刷 | 印刷 | 11/20~11/27 |
| 11/21 | OA機器の買入れ | 事務機器 | 11/21~11/27 |
上の表は、実際に東京都から発注されている案件を検索し、その「公表日」と「希望申請期間」を簡単な表にしたものです。どの案件も、公表されてから、2~3週間程度で、希望申請の提出が閉め切られてしまいます。例えば、表の一番上の「電子掲示板の買入れ」という案件について。11月6日に公表されていますが、その時点で、最短で東京都の入札参加資格を取得できるのは、翌月の1日、つまり12月1日です。しかし、12月1日には、希望申請期間が過ぎてしまっています。
そのため、公表時点で、東京都の入札参加資格(正確には「産業用機械器具類」の入札資格)を持っていないと、この案件の入札に参加することができないということになります。
それでは、東京都の入札参加資格を取得するには、どのような手続きをする必要があるのでしょうか?「申請書類を作成して、郵送すればそれで済む」というような簡単な手続きではないので注意が必要です。
まず、東京都の入札参加資格を取得するには、「入札参加資格申請」を行う必要がありますが、「入札参加資格申請」は、インターネット上の「東京都電子調達システム」というシステムを利用して行います。そして「東京都電子調達システム」を利用するには、「入札用電子証明書とICカードリーダ」を購入し、それらを使えるようにするためのパソコンの設定を行わなければなりません。つまり、東京都の入札参加資格を取得するには、電子申請が必要で、その電子申請を行うためには、「電子証明書(ICカード)」などの備品が必要になるというわけです。
また、電子申請を行うには、購入した「電子証明書」や「ICカードリーダ」を会社のパソコンで利用できるようにするための各種ソフトのインストールを行う必要があります。さらに、「東京都電子調達システム」を利用するには、東京都電子調達システムを利用できるようにするためのパソコンの環境設定、および、電子証明書の登録作業が必要になります。
このような、パソコンの環境設定手続きを経たうえで、はじめて「東京都電子調達システム」から入札参加資格の申請を行うことができるようになるわけですが、「申請書類をプリントアウトして、都庁に郵送する」といった手続きとは、比べ物にならないほど、複雑で、また面倒であるため、このような作業を、入札参加資格の申請手続きを専門に行う弊所のような行政書士事務所に外注する会社も、とても多いです。
なお、電子申請の際には、ICカードとICカードリーダをパソコンに接続し、暗証番号(PIN)を入力して、申請画面に入っていくことになりますが、途中でエラーになったり、画面が先に進まないというような場合には、パソコンの環境設定がうまく行っていない証拠です。また、申請の際には、御社の売上高や財務状況など、さまざまな数字を入力することになりますが、この数字の入力を間違えると、申請が受け付けられずに「否承認」になるパターンが多いので、注意が必要です。
行政書士法人スマートサイドでは、こうした予期せぬ事態を未然に防ぐため、電子申請のための必要事項の入力から申請完了までを一貫して代行しています。ご希望があれば、電子証明書の取得やパソコンの環境設定をご案内することも可能です。
東京都の入札参加資格を取得すると、取得した営業種目ごとに「A」「B」「C」という等級(ランク)が付与されます。「A」が一番良くて、「B」「C」と続きます。この等級は、東京都入札参加資格を電子申請した際に入力した「年間総売上高」「自己資本額」「従業員数」「流動比率」「営業年数」「障害者雇用率」「営業種目別の売上高」によって決まってきます。各審査項目を点数化し、点数の大きい方から「A」「B」「C」と等級が付与されるイメージです。
また、この等級によって発注予定金額が決まってきます。下記の表は、「営業種目:026警察・消防・防災用品」の発注標準金額一覧です。
| 等級 | 発注標準金額 | ||
|---|---|---|---|
| A | 2000万円以上 | ||
| B | 300万円以上2000万円未満 | ||
| C | 300万円未満 |
上の表からわかる通り、「営業種目:026警察・消防・防災用品」でA等級の会社は、東京都が発注する2000万円以上の入札案件に参加することが可能になります。一方で、C等級の会社は、300万円未満の入札にしか参加できないことになります。
また、実際の東京都の入札案件は、以下のように公表されます。
| 件名 | 東京都選定歴史的建造物に関する広告の制作委託 | ||
|---|---|---|---|
| 営業種目 | 116:映像等製作 | ||
| 発注等級 | B | ||
| 受付等級 | B | ||
| 申請要件 | 東京都における令和〇・〇年度物品買入れ等競争入札参加資格を有し、営業種目116「映像等製作」の「B」の等級に格付けされていること | ||
この案件では、東京都の入札参加資格のうち「116:映像等製作」の営業種目の資格を持っていることを前提に、その「116:映像等製作」の等級が「B」でなければ、申請の要件を満たさないことになります。そのため、そもそも「116:映像等製作」の入札資格を持っていない場合はもちろんのこと、「116:映像等製作」の入札資格を持っていたとしても、等級が「A」または「C」の場合には、本案件の入札には、参加することができないということになります。
なお、等級は、申請の際に東京都電子調達システムに入力した「年間総売上高」「自己資本額」「従業員数」「流動比率」「営業年数」「障害者雇用率」「営業種目別の売上高」によって決まります。この数字の入力が間違っていない(不正な入力がされていない)ことを確認するために、登記簿謄本や財務諸表を確認資料として電子送付することが必要です。
そのため、「A等級が良い」「CじゃなくてBが良い」というような希望は認められず、御社の財務状況や過去の実績を元に、客観的・画一的に決定されます。仮に「A等級が良い」という希望があったとしても、御社の財務状況や過去の実績次第では「C等級」になりうることもあります。
さて、東京都の入札資格について、「概要・種類・期限管理」など、さまざまな視点で説明してきましたが、具体的なイメージを持つことはできましたか?
行政書士法人スマートサイドは、東京都入札参加資格の申請手続きに関する専門家として、実務書の出版を行っています。
また、YouTube上には、事業者向けに「東京都入札参加資格申請(物品・委託)の概要」という90分のオンラインセミナーも公開しています。
また、私たち行政書士法人スマートサイドでは、「これから東京都の入札に参加したいけど、どこから始めればよいかわからない」という方のために、個別の有料相談(1時間11,000円)も実施しています。
この相談では
■ 資格を取得するまでのロードマップの共有
■ 電子証明書やICカードリーダの導入方法
■ 東京都電子調達システムの見方
■ 希望する資格・等級の確認の仕方
■ 申請の際に絶対に間違ってはいけないポイント
など、専門家として経験を、わかりやすく具体的にご案内させていただくことが可能です。もちろん、申請手続きのすべてをご依頼いただくこともできます。
「相談してよかった。もっと早く、相談に来ればよかった」
「自社で調べていた時間がもったいなかった。早く依頼すべきだった」
という、声を多数いただいています。
(相談概要)
| 日時 | 随時 | ||
|---|---|---|---|
| 場所 | 弊所打合せスペース | ||
| 時間 | 1時間 | ||
| 費用 | 11,000円 |
東京都の入札参加資格の申請は、「手続きが煩雑」「ルールが厳しい」「入力ミスが許されない」といった手続きです。それでも、正しい方法で資格を取得できれば、御社にとって、大きなビジネスチャンスになることは間違いありません。行政書士法人スマートサイドは、これまでに、たくさんの企業の「入札への一歩」を支援してきました。東京都の入札にチャレンジしてみたいという人は、専門家の力を味方につけて、ぜひ、一日でも早く、公共の案件を落札できるように願っています。