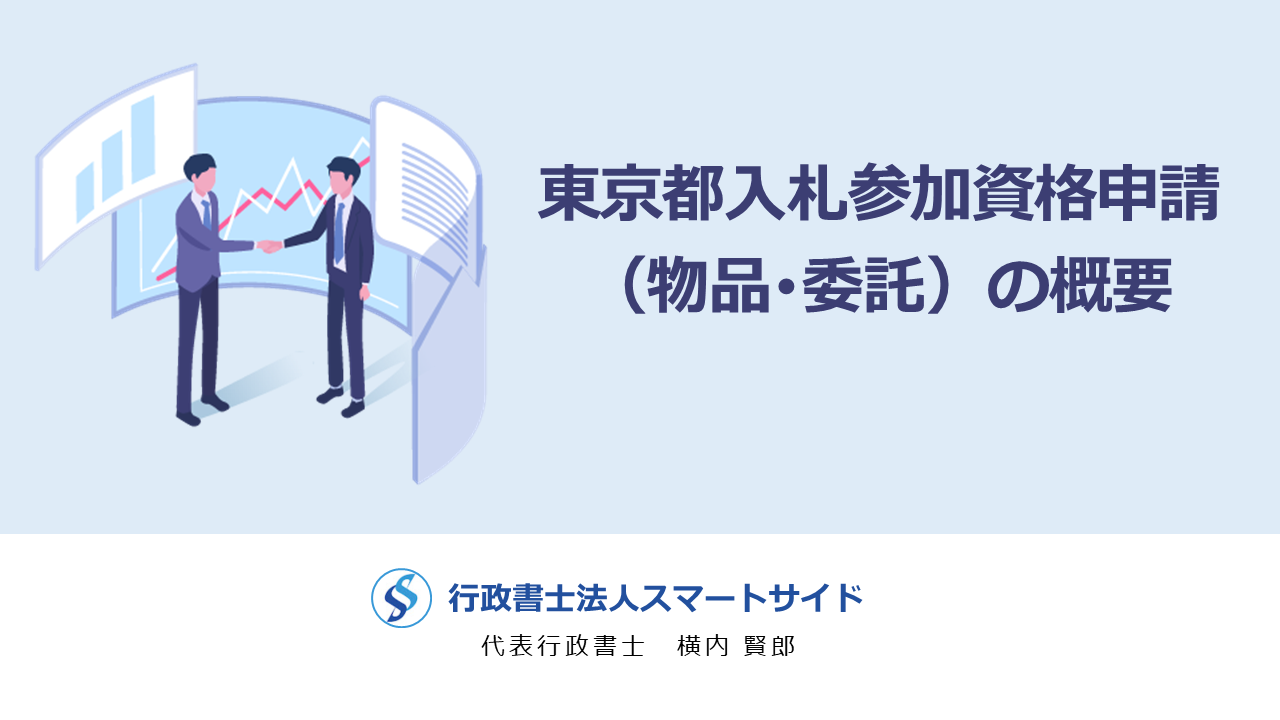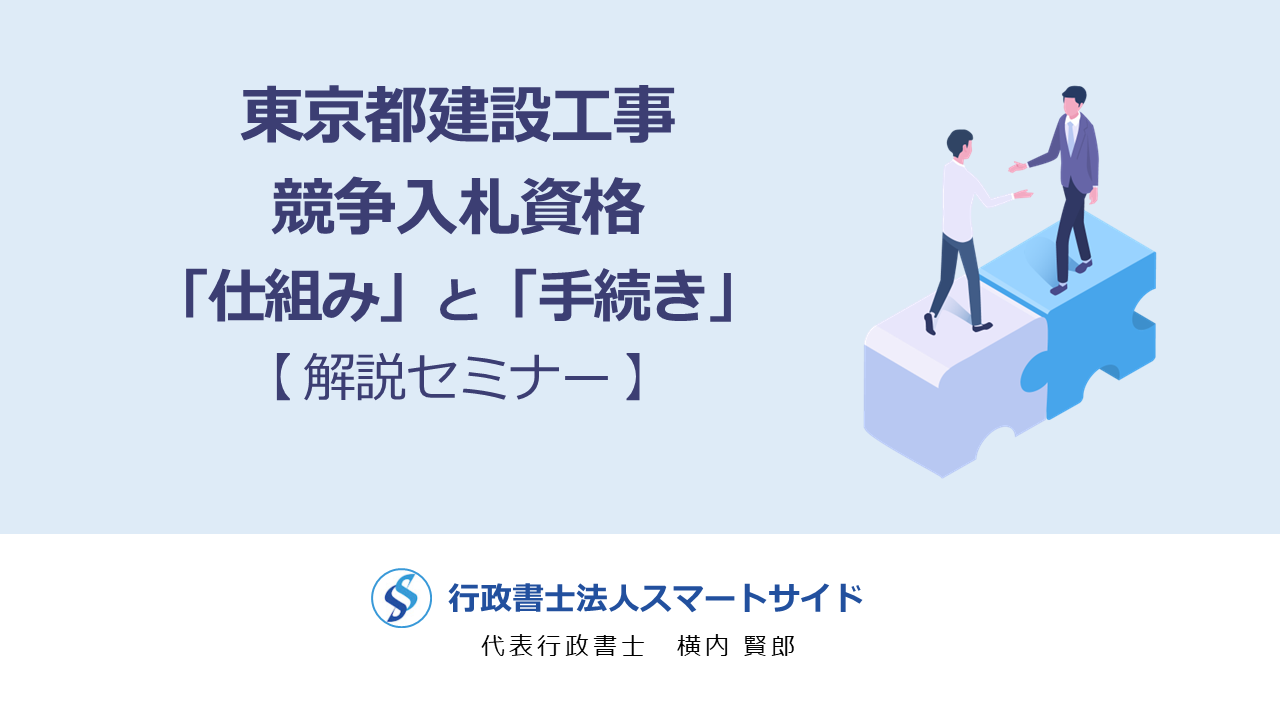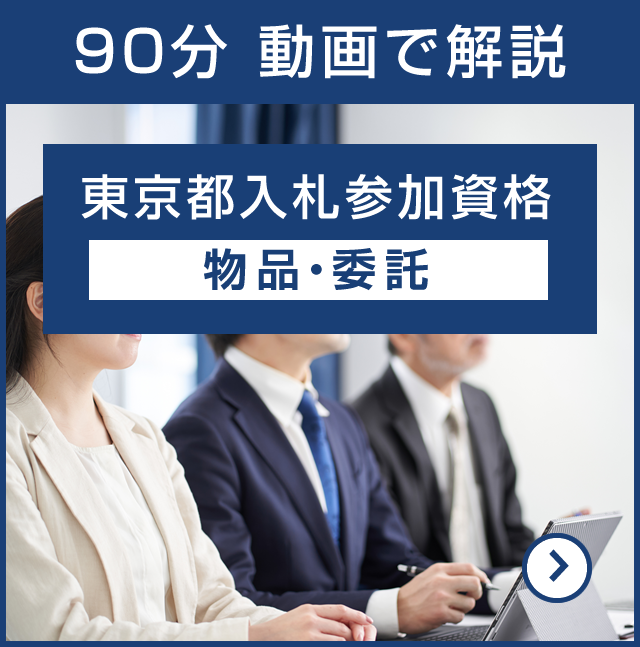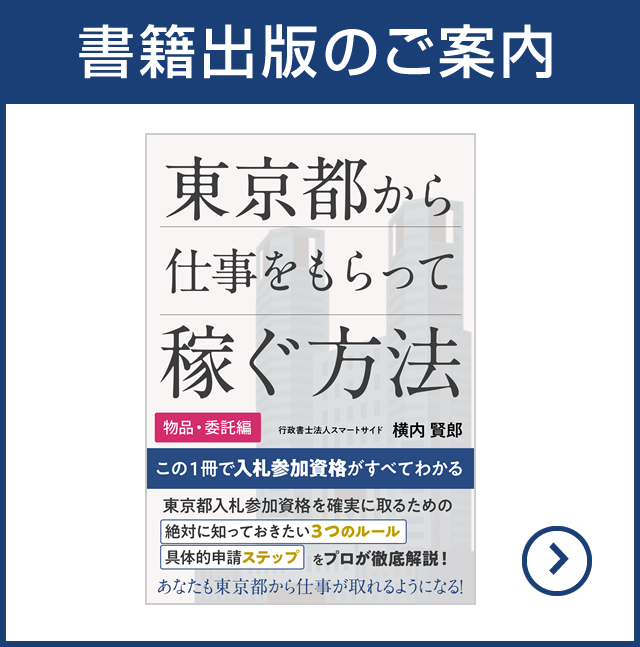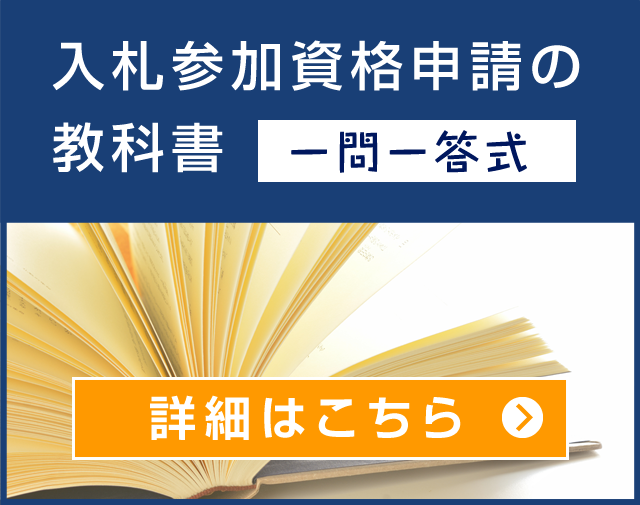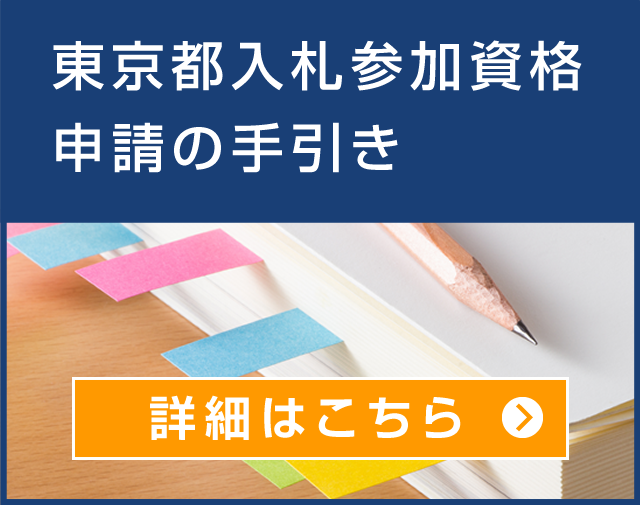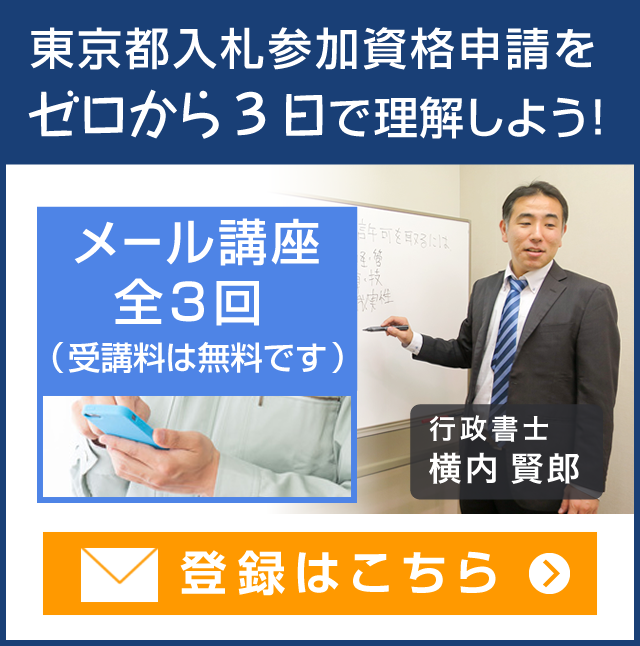プロフィール
直後に、東京都(物品・委託)の入札参加資格の手続きを依頼されたことをきっかけに、「東京都」や「全省庁」の入札参加資格申請を専門分野として、活動。新人行政書士向けに「初心者のための、東京都入札参加資格申請(物品・委託)」というテーマで、研修講師を務める。2021年10月、個人事業から法人成りし、行政書士法人スマートサイドを立ち上げ、代表に就任。
以後、東京都内の会社はもちろんのこと、東京都以外に本社がある会社からも、手続きを受任するなど、活躍の幅を広げている。入札参加資格の申請だけでなく、「電子証明書の購入申し込み・受け取り代行」「入札用パソコンの環境設定」も行うなど、お客さまの入札環境を整えて、売上アップに貢献するというのが、事務所理念。所内には、専門スタッフが複数名在籍し、大手企業からの依頼でも、チーム体制でお客さまを支援できることが強み。
2021年6月に出版した書籍「入札参加資格申請は事前知識が9割」は、初心者にもわかりやすい内容で「事前知識なしで読める」「30分程度で理解できた」と評価が高い。
| 所属 | 東京都行政書士会 文京支部 |
|---|---|
| 行政書士番号 | 14081063号 |
| 事務所 | 行政書士法人スマートサイド 代表行政書士 |
東京都の入札資格申請の解説動画
入札環境を整えて、売上アップに貢献
- 民間との取引のほかに、役所との取引を視野に入れて、事業を伸ばしていきたい
- 公共事業に参入して、安定的・継続的に売り上げを確保していきたい
経営者であれば、だれでも一度は、役所との取引に興味を持ったことはあるのではないでしょうか?実は、東京都は、年間6000件以上の公共事業を発注しています。また、公共工事を除いた物品・委託の分野では、67個もの営業種目が用意されていて、自社の事業内容に合致した多様な案件への入札が可能になっています。具体的には「文房具事務用品」「事務機器」などの『物品』と「建物清掃」「広告代理」などの『委託』に分かれています。
そんな東京都の入札ですが、「誰でも・自由に・いつでも」参加することができるわけではありません。ここが、多くの人が勘違いしているところです。東京都の入札に参加するには、事前に、入札用の電子証明書を購入し、各種パソコンの環境設定を行ったうえで、入札参加資格を電子申請し、かつ、承認を得なければならないのです。いますぐ、入札に参加したいと思っても、実際に準備を始めてから、入札に参加できるようになるまでには、早くても1か月以上、通常2か月程度、余裕を見ておかなければなりません。
そんな面倒な手続きですが、自社で行うことは、あまりお勧めできません。なぜなら、知識が不足したまま、手引きやマニュアルをよく理解せず入札資格を取得したことによって、かえって案件受注から遠ざかる、取返しのつかない失敗をしているということがあるからです。たとえば、「営業種目の選択ミス」や「等級格付が無格付けになってしまう」ということがあります。残念ながら、こういったミスは、知識のない人がリスクを認識しないまま、手続きを進めてしまった結果に他なりません。
- 電子証明書の購入申し込み/受け取り代行
- パソコンの環境設定
- 東京都電子調達システムへの電子証明書の登録
- 東京都入札参加資格の電子申請
- 承認/否承認の確認や、受付票/結果通知書のプリントアウト
に至るまで、東京都の入札参加資格の取得について、一切の手続きを御社に代わって代行します。これは「お客さまの入札環境を整えて、売上アップに貢献すること」を事務所の使命として掲げているからにほかなりません。
弊所のお客さまの中には、9億円の東京都の委託事業を落札したお客さまがいらっしゃいます。また、4億円の東京都の公共工事を落札したお客さまもいらっしゃいます。数百万円~数千万円という単位だと、数え上げたらきりがないくらいの会社が、弊所のサポートを受けて、東京都の公共事業を受注しています。
さあ、つぎは、御社の番です。面倒で煩わしい入札資格の取得手続きは、弊所のような専門家に外注し、公共案件の受注活動に専念してください。
入札に関する書籍の出版実績
オンラインセミナー
インタビュー記事の掲載
| 東京都入札参加資格申請の成功のプロセスと着眼点 |
| 東京都入札参加資格の必要書類とは?事前準備のポイントを解説 |
| 東京都入札参加資格の営業種目とは?選び方と注意点をわかりやすく解説 |
| 東京都の入札資格「等級・格付」の仕組みを徹底解説 |
| 東京都内の区・市で入札に参加するには?入札参加資格申請の流れをわかりやすく解説 |