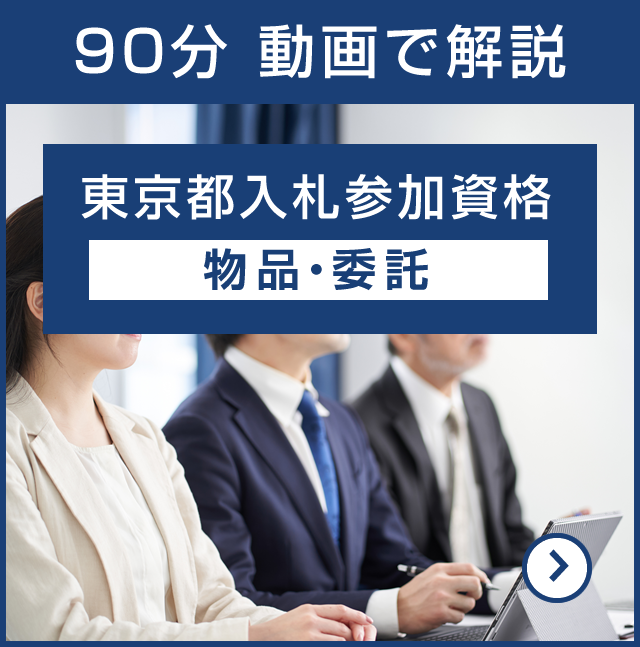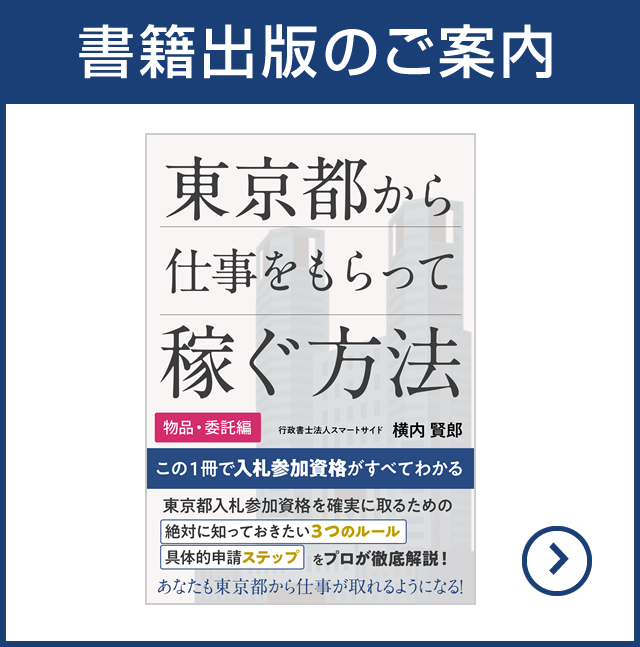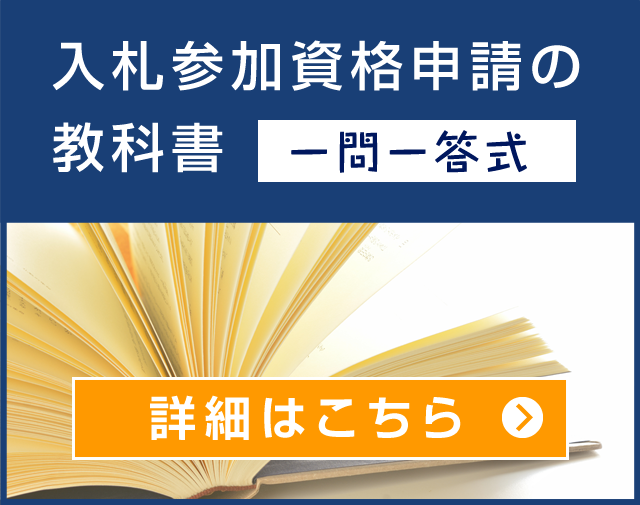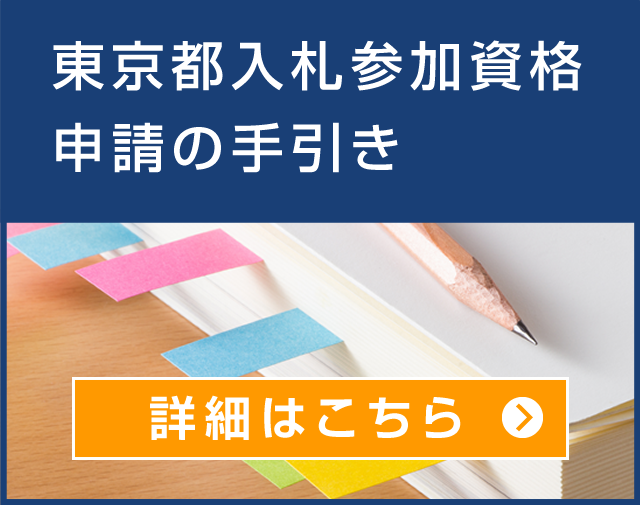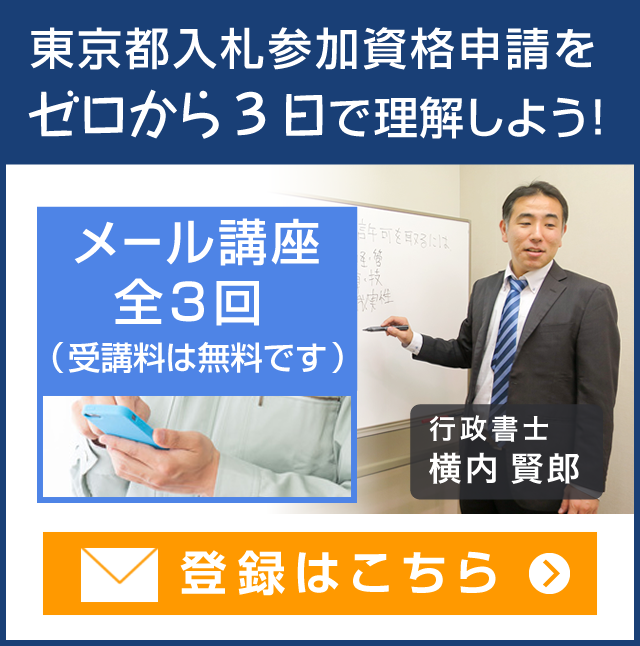そこで今回は、東京都の入札参加資格申請を数多く支援してきた専門家、行政書士法人スマートサイドの代表行政書士・横内賢郎先生に、営業種目と取扱品目の基本、選定時の注意点、よくある誤解などについて詳しくお話を伺いました。
東京都入札参加資格の「営業種目」「取扱品目」とは?
それでは、横内先生。本日も、よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。今日のテーマは、東京都の入札資格(物品・委託)の「営業種目」についてですね。かなり細かいテーマですが、「営業種目を何にするか?」という選択は、とても重要ですので、しっかりとわかりやすく解説していきたいと思います。

まず、「営業種目」と「取扱品目」の説明から始めます。
東京都の入札参加資格を取得するには、「営業種目」「取扱品目」を選択しなければなりません。なお、東京都の入札参加資格には公共工事の分野もありますが、今回は『物品の販売』や『役務の提供』に関する資格申請に限定してお話しします。
東京都の手引きに沿って説明すると、「物品」には全部で30個の営業種目があり、「委託等」には全部で37個の営業種目があります。たとえば、物品の中には「003:学校教材・運動用品・楽器」や「026:警察・消防・防災用品」といった営業種目があります。また、委託等の中には「101:印刷」や「105:警備・受付」や「121:情報処理業務」といった営業種目があります。
東京都の公共工事以外の入札資格は「物品」と「委託等」に分かれていて、そして、さらに「物品」の中には30の営業種目が、「委託等」の中には37の営業種目があるという認識で良いですね。
はい。とてもよく理解できています。その認識で間違いありません。
「営業種目」を「大分類」とすると、「取扱品目」は「小分類」と捉えることができます。たとえば、先ほどの「物品」の中の「026:警察・消防・防災用品」という営業種目の中には、「09避難器具」や「16災害用備蓄食糧」や「19警察装備品」といった13個の「取扱品目」があります。
また、「委託等」の中の「121:情報処理業務」という営業種目の中には、「01データ入力・消去」や「04ホームぺージ作成・管理」や「09専門情報提供サービス」といった10個の「取扱品目」があります。
各「営業種目」の中に、複数の「取扱品目」が含まれているので、入札参加資格申請を行う際には、大分類である「営業種目」を選ぶだけでなく、その中に含まれている「取扱品目」(小分類)も選ばなければなりません。
私の事務所のホームページには、「物品」の「営業種目・取扱品目」と、「委託等」の「営業種目・取扱品目」をまとめたページがありますので、気になる方は、ぜひ、そちらのページを参考にしてみてください。
(参考)「東京都入札参加資格(物品)の営業種目・取扱品目の一覧」は、こちら
(参考)「東京都入札参加資格(委託)の営業種目・取扱品目の一覧」は、こちら
「営業種目」は、多く選択した方が有利なのか?
「営業種目」と「取扱品目」については、よく理解できたのですが、少しでも多くの案件を落札したい会社は、より多くの「営業種目」を選択して申請した方が、有利ということになるのでしょうか?

とてもよい質問です。東京都が発注している案件の詳細を見たことがある人なら分かると思うのですが、東京都は、『東京都における「令和〇年度の競争入札資格」を有し、営業種目「026:警察・消防・防災用品」の資格を有していること』といったように、営業種目ごとに案件を発注しています。
そのため、より多くの営業種目を選択した方が、入札に有利であるというように思うかもしれません。しかし、実際は、そうではないことの方が多いです。
それは、どういうことでしょう。「営業種目の数は、多ければ多いほどよい」というものではないのですか?
選択する「営業種目」の数は、多ければ多いほどよいというわけではありません。
まず前提として、選択することができる営業種目は、全部で10個までと決まっています。これは、「物品」と「委託等」を合わせて、全部で10個という意味です。東京都の物品・委託等の営業種目は、全部で67個ありますが、申請できる営業種目は、最大でも10個までと限られています。また、取扱品目は1営業種目について、8個までです。
まずは、こういった数字上の制限があることを理解してください。
さらに、申請する際には、前年度の売上高を営業種目ごとに割り振らなければなりません。仮に、選択した営業種目の中に、売上高0円のものがあったとすると、その営業種目は「無格付(X)」となって、積極的に入札に参加することができなくなってしまうのです。
「無格付(X)」とは?
「無格付(X)」ですか?これは、どういうことでしょう。
この点について、素人の人は、少しわかりづらいかもしれませんので、丁寧に説明させて頂きますね。
まず、東京都の入札参加資格を申請すると、営業種目ごとに「Aランク・Bランク・Cランク」という等級が付与されます。これを等級格付と言ったりします。この格付は、「何を基準」に行われるか?というと、「前年度の売上高を基準」に行われます。大まかにいうと、営業種目ごとに、前年度売上高が、「300万円未満の場合は、Cランク」「300万円~3000万円未満は、Bランク」「3000万円以上は、Aランク」というように格付が行われます(※)。
等級格付としては、営業種目ごとの売上高が多い方が有利になります。
一方で、前年度の売上がない営業種目を選択することもできます。しかし、売上がないので、いま述べた「A」「B」「C」というランクが付与されることはなく、売上高0円の営業種目は、「無格付(X)」となってしまうのです。そして、「無格付(X)」となると、その会社の履行能力や実績が不明なため、東京都は、営業種目の格付が「無格付(X)」の会社に対しては、「積極的に指名を行うことはない」とされているのです。
そうすると、無理に営業種目をたくさん選ぶよりも、より高いランクが狙えるものに絞って、東京都の資格を取得した方が、有利ということが言えそうですね。
まさに、その通りです。
このインタビューの冒頭に、私は、全部で10個の営業種目を選択できるという話をしました。しかしながら、前年度の売上が0円で売上実績が無い営業種目をたくさん選んだところで、東京都の入札に参加できる可能性は、きわめて低いのですから、わざわざ、そういった営業種目にまで、幅を広げて、申請していく必要性は、ないと考えています。
もちろん中には、戦略的に「最多10営業種目」を申請したお客さまも、いらっしゃいます(※)。しかし、特殊な事情がない限り、選択する営業種目は、多くても4つ程度であることが多いです。自社の得意分野や専門分野に絞って、案件を狙っていくのが、入札戦略として常識である以上、あえて、自社の不得意な分野や専門外の分野の営業種目を選択する必要はないはずです。
弊所のお客さまでも、もっとも多いのが2~3個程度です。営業種目を5以上選択するお客さまは、きわめて稀であるというのが実際のところです。
(※参照)「東京都の入札資格を『最多10営業種目』申請する際のメリット・デメリットと注意点を専門家が詳細解説」のページは、こちら
「営業種目」の訂正・変更・追加について
なるほど、営業種目は、2つか3つ選択する会社が多いのですね。数を増やしたからといって入札に有利になるわけではないということがよく理解できました。それでは、他に、営業種目を選択する上で、注意点みたいなものはありますか?
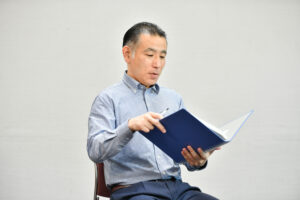
はい。この注意点については、私の事務所のホームページでも、他のインタビューでも再三にわたって、繰り返しているので、どこかで聞いたことがある人がいるかもしれませんが、とても、重要なことなので、再度お話しますね。
それは、「一度、選択した営業種目・取扱品目は、資格の有効期間中、変更・追加・訂正することができない」という点です。この点については、年に数件、必ず、「どうにかなりませんか?」という相談を頂くくらいに、みなさん、間違えることが多い事項です。
先ほど、お話したように、東京都の入札参加資格は、67個の営業種目の中から、最大で10個まで選んで申請することができます。MAXである10個を選択する会社は、ほとんどおらず、多くの会社は、自社の得意分野に絞って、2,3個を選択します。大事なのは、申請時に選択した、その営業種目は、あとになってから変更や追加ができないのです。
たとえば、みなさんの会社が「115:広告代理」「116:映像等製作」「121:情報処理業務」の3つの営業種目を選んで、東京都の入札参加資格を申請したとします。しばらく経って、東京都からお目当ての案件が発注されたので、ぜひ、この案件を落札したいと思って、案件の詳細を確認したところ、その仕様書には「営業種目『120:催事関係業務』で東京都の入札資格を持っていること」という条件があったとします。この場合、「120:催事関係業務」の営業種目で入札資格を持っていないみなさんの会社は、この案件の入札に参加することができません。
このようなケースにおいて、今後同じような案件が発注された場合、次回以降その案件の入札に参加することができるように「120:催事関係業務」の営業種目を追加したいと思うのが通常でしょう。しかし、それができないのです。「115:広告代理」「116:映像等製作」「121:情報処理業務」に「120:催事関係業務」を追加することもできなければ、「115:広告代理」「116:映像等製作」「121:情報処理業務」のどれか1つと「120:催事関係業務」を変更することもできないのです。
それは、とても厳しいですね。そうすると、この会社の場合、今回の資格の有効期間中は、東京都が発注する「120:催事関係業務」の入札には参加できないということでしょうか?
はい。
この場合、この会社は、資格の有効期間中は、「120:催事関係業務」の入札に参加することはできません。
それでは、一度取得した資格を取り消して、全部、最初からやり直すという方法は、どうでしょう?このケースでいうと、「115:広告代理」「116:映像等製作」「121:情報処理業務」を全部取り下げて、再度、「115:広告代理」「116:映像等製作」「121:情報処理業務」に「120:催事関係業務」を追加した4つの営業種目で申請をし直すという方法が、考えられると思うのですが…
残念ながら、そういった方法も認められていません。
東京都の手引きには、明確に「資格有効期間中に資格を取り消し(申請を取り下げ)た場合、同有効期間中に再申請(随時申請等)をすることができません。」と記載されています。
先ほどの例で言うと、この会社が「120:催事関係業務」の営業種目を取得することができるのは、次回の更新の際に、「120:催事関係業務」を選んで申請し、その資格が有効になってからということになります。
手引に明確に記載されているとは言え、こういったルールを理解できている人は、非常に少ないのではないでしょうか?
そうですね。「手引きを見れば書いてある」と言われれば、その通りかもしれないのですが、実際に、どれだけの人が、手引きを熟読して申請しているか?という点が問題です。こういった点については、私たちのような専門家が、正確な情報を発信し続けて、事業者のみなさんが、間違った申請をして不利益を被ることがないよう、注意喚起を続けていく必要があると思っています。
横内先生。ありがとうございます。それでは、お時間になりましたので、最後に一言お願いできますでしょうか?
本日のテーマである「営業種目」について、慎重な対応が必要になるということをご理解いただけましたか?
時々、お客さまの中にも
- 営業種目は、適当に選んでおいて欲しい…
- なにか儲かりそうな営業種目は、ありますか?
- 簡単に落札できる営業種目が良いのですが!
という発言をされる人がいらっしゃいます。そういった人は、今まで話して来たことや、手引きの記載を理解できていない可能性があるので、要注意です。
東京都の入札に参加するわけですから、「営業種目」や「取扱品目」は、会社の得意分野や専門分野の中から選択するべきであって、自社の得意分野や専門分野がわからない人はいないと思います。また、社長一人で決めるのではなく、営業部や開発部を巻き込んで、入札に参加しようとする会社がある一方で、「なんの営業種目を選択すればよいのか自分で決められない」というのは、いかがなものでしょうか?
そういった場合の対策として、「発注機関である東京都に聞いてみる」「同業他社の入札資格の取得状況を調べてみる」という方法もあります。営業種目の選択を他人任せにするより、よほど、確実で確かな方法です。
また、行政書士法人スマートサイドでは、東京都の入札資格の手続きでお困りの人に、事前予約制の有料相談を実施しています。わからないことや困ったことがあれば、有料相談をお申し込みいただけばと思います。
それでは、本日は、長い時間、ありがとうございました。