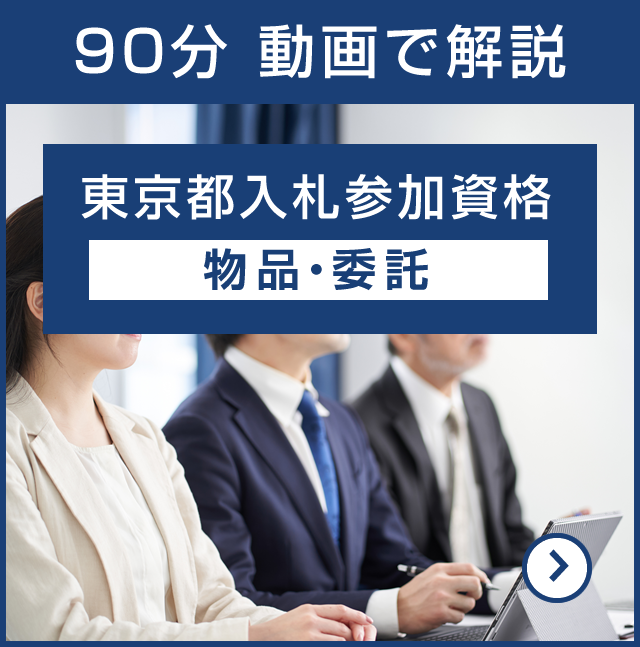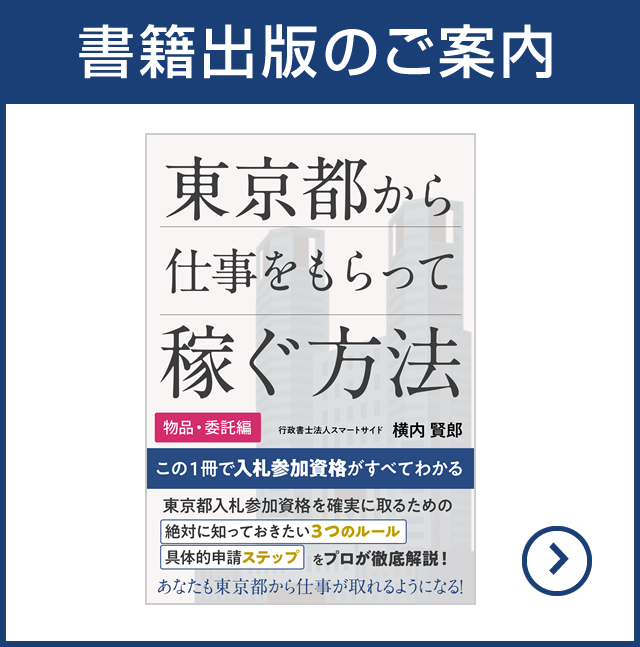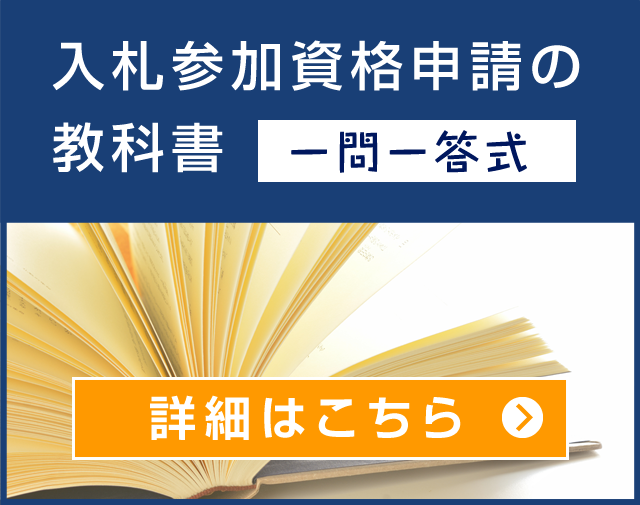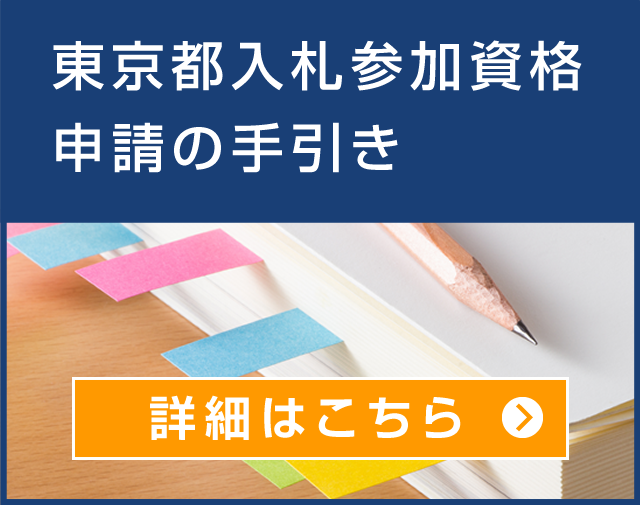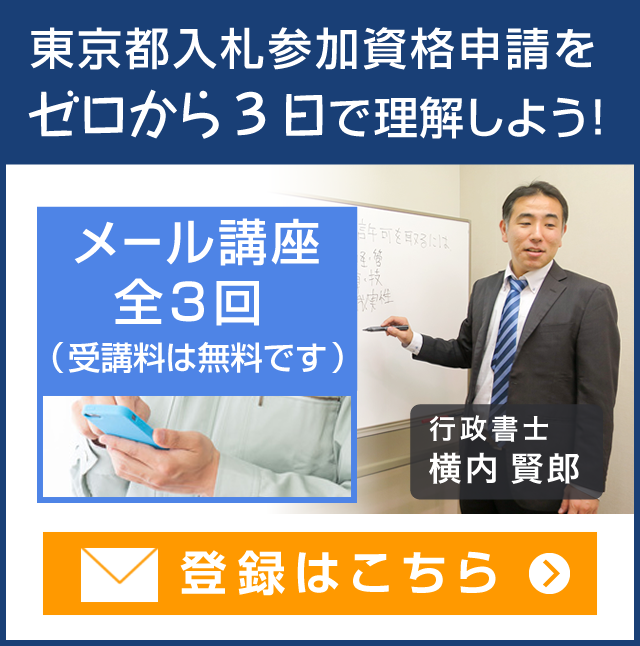■ 東京都の入札資格を取得する?
■ 区市町村の入札資格が必要?
入札参加資格の取得を検討している会社のなかには、「東京都の入札資格」と「区市町村の入札資格」の違いがよく分からず、どちらを取得すべきか迷っている方も少なくありません。実は、東京都と区市町村の入札資格は、まったくの「別物」であるため、両者には大きな違いがあります。今回は、数多くの企業の入札参加資格申請をサポートしてきた専門家、行政書士法人スマートサイド代表の横内賢郎先生に、東京都と区市町村の入札制度の違いや、申請時に気をつけるべきポイントを詳しく伺いました。初めての方でも分かりやすい内容になっていますので、ぜひ参考にしてください。
東京都と区市町村の入札資格は、まったくの別物
それでは、横内先生。本日は、「東京都」と「都内区市町村」の入札参加資格の違いについて、お話を聞かせて頂けますでしょうか?
はい。承知しました。本日も、よろしくお願いします。

今日のテーマは、『「東京都」と「都内区市町村」の入札資格の違い』についてですが、そもそも、「東京都の入札」と「区市町村の入札」が全くの別物であるという点について、理解できていない人もいるかと思うので、まずは、その点から、説明を始めていきたいと思います。
「東京都」と「区市町村」は、まったくの別物――それは、どういう意味でしょう?
はい。
弊所にご相談に見えるお客さまの中には、
- 東京都の入札資格を持っていれば、渋谷区や三鷹市の入札に参加することができる
- 都内区市町村の入札資格を持っていれば、東京都が発注する案件に参加することができる
- 東京都と区市町村の入札資格は、一緒である
と誤解している人が非常に多いです。しかし、これは明確な誤りです。
たとえば、東京都が発注する案件に参加したいのであれば、東京都の入札参加資格を持っていなければなりません。足立区や千代田区が発注する案件に参加したいのであれば、足立区や千代田区の入札参加資格を持っていなければなりません。東京都の入札参加資格を持っているからと言って、足立区・千代田区の入札に参加することができるわけでもなければ、足立区や千代田区の入札参加資格を持っているからと言って、東京都が発注する入札案件に参加することができるわけでもないのです。
なるほど、「都」もしくは「区」が発注する案件に参加するには、それぞれの入札資格を持っていなければならないということですね。
おっしゃる通りです。
ここで注意しなければならないのは、東京都の入札参加資格を取得するには、「東京都電子調達システム」という東京都のホームぺージから電申請を行う必要があります。一方で、区市町村の入札参加資格を取得するには、「東京電子自治体共同運営電子調達サービス(略して、e-Tokyo)」のホームぺージから電子申請を行う必要があります。
「東京都の入札資格」と「区市町村の入札資格」の違い
申請の方法が異なるということですか?
はい。申請の方法が異なるどころか、申請のルール、必要書類、資格の有効期間に至るまで、何から何まで違います。

まず、東京都が発注する案件の入札に参加したいのであれば、東京都の入札参加資格が必要で、その資格を取得するには「東京都電子調達システム」から電子申請を行う必要があるという点は理解できましたね。おなじように、都内区市町村が発注する案件の入札に参加したいのであれば、都内区市町村の入札資格が必要で、その資格を取得するには「東京電子自治体共同運営電子調達サービス(e-Tokyo)」から電子申請を行う必要があるという点についても同じです。
東京都の場合、資格の有効期間は、最大で2年間です。2年度ごとに更新手続きが必要になります。これに対して、区市町村の場合、資格の有効期間は、直近の確定した決算から起算して1年8か月です。そのため、区市町村の場合は、毎年更新手続きが必要になります。
このように、東京都の更新手続きは「2年に1度」でよいのに対して、区市町村の更新手続きは「1年に1回」行わなければならないという違いがあります。
有効期間の違いですね。ほかにありますか?
はい、ほかには申請期限についての違いもあります。
東京都の場合、毎月10日ころまでに申請を行えば、翌月1日から東京都の入札に参加することができます。これに対して、区市町村の場合、毎月25日までに承認されれば、翌月1日から区市町村の入札に参加することができます。このように、申請のタイミングや受付期限、さらには、資格適用開始日も異なりますので、スケジュール管理には注意が必要です。
また、申請を行う際の必要書類についても違いがあります。
東京都の場合「履歴事項全部証明書」と「財務諸表」だけで良いのですが、区市町村の場合「履歴事項全部証明書」と「財務諸表」に加えて「法人事業税納税証明書」「法人税納税証明書」「消費税納税証明書」という3つの納税証明書が必要になります。
全59の都内区市町村の入札参加資格の取得
東京都と区市町村の違いは、よく分かりました。ちょっと質問なのですが、たとえば「新宿区」「杉並区」「世田谷区」の3つの特別区の入札参加資格を取得したいと考えた場合、それぞれ3つの区への申請手続きが必要になるのでしょうか?
とてもよい質問です。
「東京電子自治体共同運営電子調達サービス(e-Tokyo)」の中身について、お話をさせて頂きますね。実は、「東京電子自治体共同運営電子調達サービス(e-Tokyo)」は、1回の申請で『23の区、26の市、4つの町、3つの村、東京二十三区清掃一部事務組合、多摩川衛生組合及び多摩ニュータウン環境組合』という全部で59の自治体の入札資格を取得することができるのです。
ですので、弊所にご依頼いただくお客さまのほとんどは、よほどの事情がない限り59の自治体のすべての資格を取得しています。もちろん、「渋谷区だけでいい」とか「練馬区と板橋区だけでよい」というように限定して申請する人もいらっしゃいます。しかし、59の自治体のすべてを選んだからと言って、申請手続きを59回繰り返さなければならないわけではありません。また、書類を59通そろえる必要があるわけでもありません。
申請する際に、希望の自治体にチェックを入れて申請するだけなので、1つの自治体に絞ろうが、59全ての自治体に申請しようが、手間自体は、まったく変わらないのです。
そういうことでしたか?であれば、59の自治体すべてに申請して、都内区市町村のすべての自治体の入札参加資格を取得した方が、案件落札の可能性も増えるように思えて、得した気分になります。
その点については、すこし注意が必要です。
たしかに「東京電子自治体共同運営電子調達サービス(e-Tokyo)」を使用すれば、東京都内の区市町村(全59の自治体)の入札参加資格を1回の手続きで取得することができます。しかし、入札参加資格を取得したからといって、必ず、案件に参加することができるとは限らないのです。
たとえば、中央区が発注する案件には「中央区内に本店・支店・営業所があること」とか、豊島区が発注する案件には「豊島区内に本店・支店・営業所があること」といったように、「本店・支店・営業所が区内にあること」を条件に、案件への入札参加を認める場合が非常に多いのです。
この場合、中央区や豊島区の入札参加資格を持っていたとしても、中央区や豊島区内に「本店や支店や営業所」がなければ、その案件には参加することができないことになります。
これが、先ほど、申し上げた「入札参加資格を取得したからといって、必ず、案件に参加することができるとは限らない」ということの意味です。
なるほど、そういった「場所的な条件」みたいなものがあるんですね。
この点については、実際に、各特別区や市町村から発注される案件を見てみないことには、なんとも言えませんが、「場所的な条件」は、かなり多いと聞きます。入札参加資格を取得する際には、そのあたりのことも頭に入れたうえで、どの自治体の入札資格を取得したら良いのかの検討をして頂ければと思います。
「東京都」と「区市町村」の両方の入札に参加したい場合
それでは、「東京都の入札参加資格も欲しいし、区市町村の入札参加資格も欲しい」場合は、どうすればよいのですか?
その場合には、「東京都電子調達システム」から東京都の入札参加資格の申請を行い、「東京電子自治体共同運営電子調達サービス(e-Tokyo)」から区市町村の入札参加資格申請と行う必要があります。2つの手続きを行う必要があるのです。先ほどからお伝えしているように、この2つは、まったくの別物と考える必要があります。

「システムの作り」や「入力項目」に似ている箇所はあります。しかし、たとえば
- 東京都と区市町村では、営業種目や取扱品目が異なること
- 区市町村の場合、民間の契約実績まで入力する必要があること
- 従業員の人数の考え方が、都と区では異なること
など、細かな違いがあります。なので、別々の手続きととらえて、1つ1つ丁寧に申請していくよりほかないといった感じです。以前、お客さまから「東京都と区市町村の入札資格をまとめて取る何か良い方法はないのか?」という質問を受けたことがありますが、「何か良い方法」というのはなくて「東京都電子調達システム」と「東京電子自治体共同運営電子調達サービス(e-Tokyo)」をそれぞれ使い、1つずつ丁寧に申請していくしか方法はありません。
そうすると、「東京都の入札参加資格も欲しいし、区市町村の入札参加資格も欲しい」場合、電子証明書やICカードリーダも別々に用意しないといけないのですか?
いいえ。
東京都の入札参加資格を取得する際にも、都内区市町村の入札参加資格を取得する際にも、電子証明書とICカードリーダの購入は必須です。しかし、電子証明書は1枚、ICカードリーダは1台あれば、同じものをお使いいただくことができます。そのため、東京都と区市町村の2種類の入札参加資格を取得するからと言って、電子証明書を2枚用意する必要はありませんので、ご安心ください。
ただ、冒頭から話しているように、東京都と区市町村は、それぞれ別のシステムを使って、入札参加資格を申請する必要があります。そのため、電子証明書やICカードリーダが使えるようにするためのパソコンの設定が必要なのはもちろんのこと、「東京都電子調達システム」が使えるようにするためのパソコンの設定、「東京電子自治体共同運営電子調達サービス(e-Tokyo)」が使えるようにするためのパソコンの設定も必要になります。
これは、東京都と区市町村とで、使用しているシステムが異なる以上、しょうがないことだと思います。なお、入札参加資格申請の手続きの流れについては、別のインタビュー記事をホームページ上に公開しておりますので、興味がある方は、そちらを参考にして頂ければと思います。
(参考)「【専門家インタビュー】東京都入札参加資格申請の流れを徹底解説!初めてでも迷わない」は、こちら
『「東京都の資格」と「区市町村の資格」を、同時に取得したい』というお客さまは、いらっしゃいますか?
はい、もちろん、そういったお客さまは、多くいらっしゃいます。
とくに、新しく営業活路を見出したい会社や、社長が役所との取引に乗り気な会社は、東京都だけでなく区市町村の入札にも参加したいと意気込んで相談に見える場合もあります。
弊所では、東京都だけでなく、区市町村の入札参加資格申請にも対応しているので、そういったご要望には、十分に対応することが可能です。
東京都と区市町村の資格の両方を同時に取得するのは、とても難しいそうなので、横内先生のような専門家にお願いするのも1つの手段かもしれませんね。そろそろ、お時間になりましたので、最後に、ひとことお願いします。
このインタビューでお話したように、「東京都の入札参加資格」と「区市町村の入札参加資格」とは、まったくの別物です。もちろん、「東京都に絞って、入札参加資格を取得する」とか「台東区の入札参加資格だけでよい」といったように、対象を絞って申請するのも良いでしょう。一方で、「この機会に、東京都と全区市町村の入札参加資格を取得したい」という意欲に満ちた人もいると思います。
そういった場合には、ぜひ、行政書士法人スマートサイドへの手続きの依頼を検討してみてください。
弊所では、電子証明書の取得や、パソコンの環境設定や、必要書類の収集など、「東京都」にも「区市町村」にも対応できる体制を整えています。
このインタビューが、みなさんの入札参加資格取得の一助になれば幸いです。