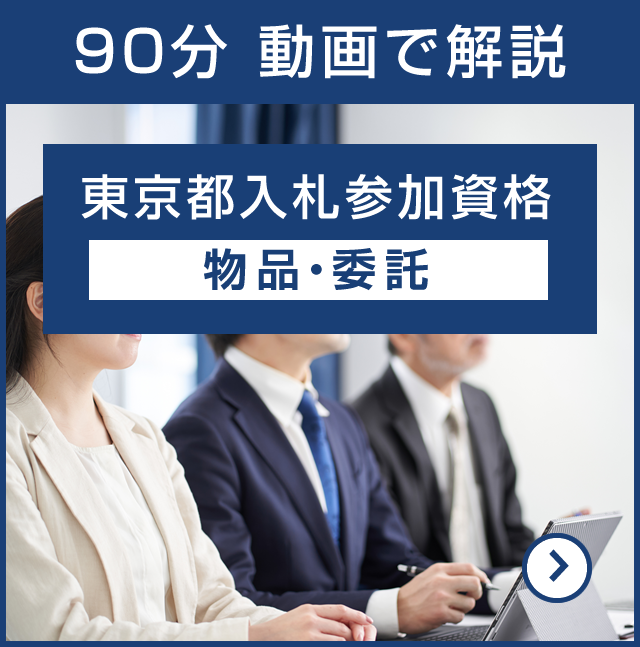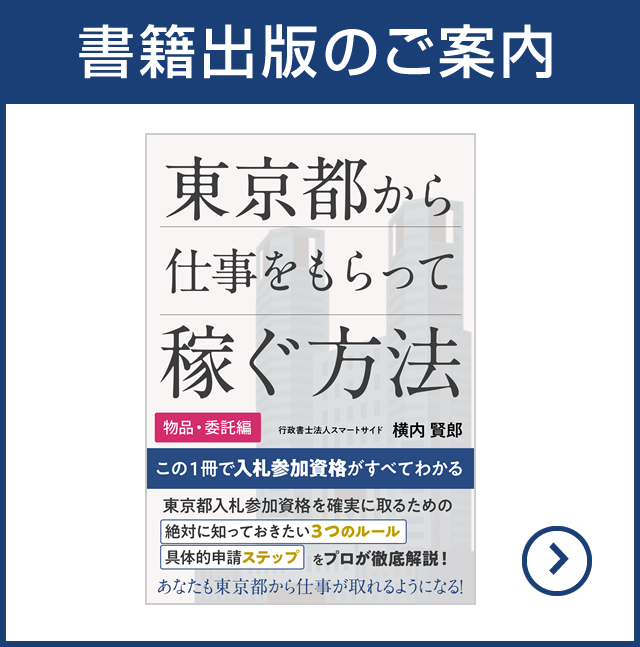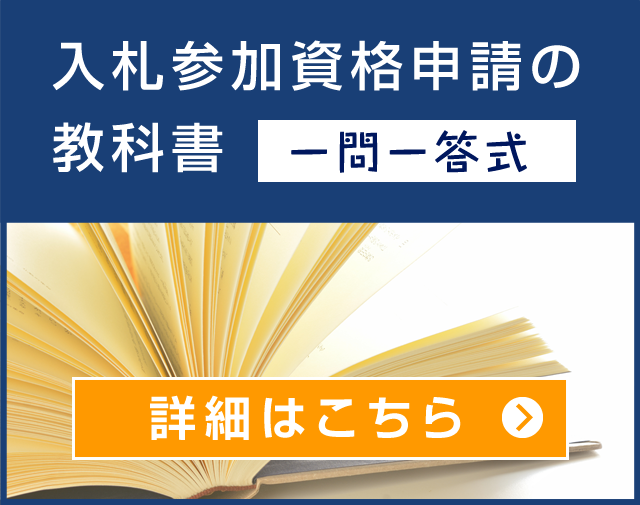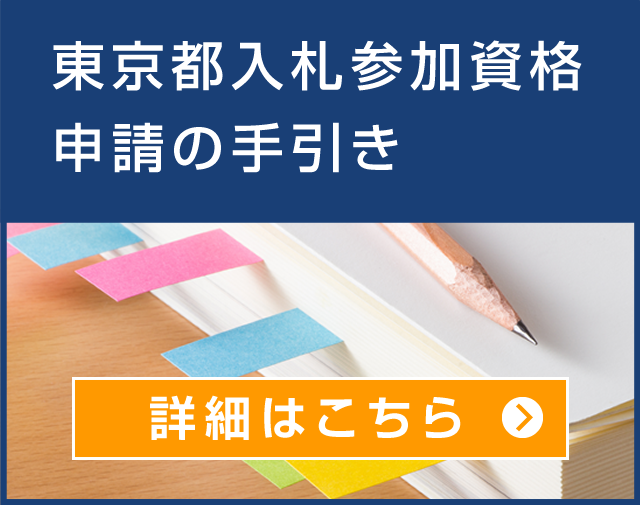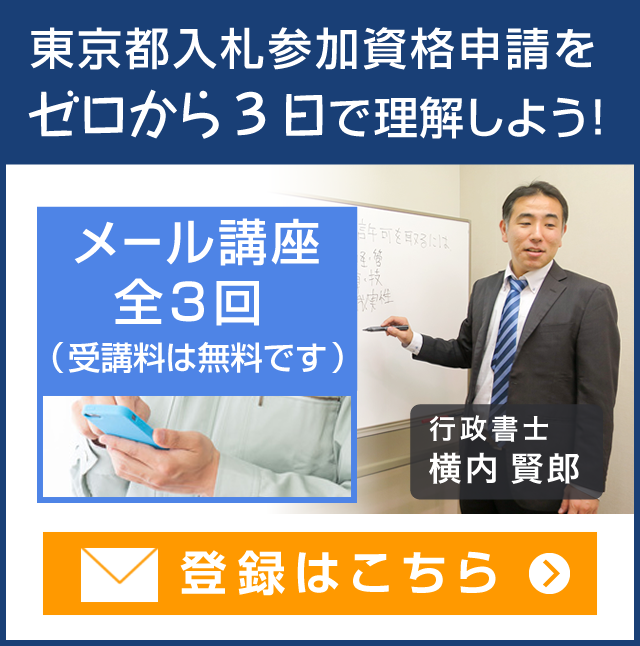東京都の入札に参加するには、入札参加資格を取得するだけでなく、「等級(ランク)・格付」の仕組みを正しく理解することが欠かせません。なぜなら、発注される案件の多くは、等級によって参加できる会社があらかじめ限定されているからです。等級を正しく把握していないと、「せっかく資格を取ったのに入札できない」という事態にもなりかねません。
今回は、東京都の入札参加資格申請を多数支援してきた専門家、行政書士法人スマートサイドの代表行政書士・横内賢郎先生に、等級・格付の基本から実務上の注意点まで、詳しくお話を伺いました。初めて等級制度に触れる方にも分かりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
東京都の入札の「等級」について
それでは、横内先生、本日は、東京都の入札参加資格における「等級・格付」というテーマで、お願いします。
今日もよろしくお願いします。
「等級・格付」は、「何となく知っている」とか「聞いたことはある」という人はいても、実際に、「どういう基準が定められていて、どうやって算出されているのか?」について、理解されている人は少ない印象です。ですので、このインタビューで、しっかり理解して頂けるように、説明して行きたいと思います。

また、今回は、東京都の入札資格のうち、物品や委託を題材にしています。公共工事の「等級・格付」については、以前のインタビューでお答えしていますので、建設会社や公共工事の入札に興味がある人は、ぜひ、以前のインタビュー記事を参考にして頂ければと思います。
(参考)【専門家に聞く】建設会社必見!東京都公共工事「等級格付基準」の核心に迫る
(参考)【専門家に聞く】東京都の公共工事の等級制度とランクアップの秘訣
「公共工事」の場合と、「物品・委託」の場合とでは、等級や格付に関する基準が違うのですね。
はい。同じ東京都の入札参加資格であったとしても「公共工事」と「物品・委託」とでは、まったく異なりますので、今回は、「物品・委託」について、お話させて頂きます。
まずは、等級についてです。
東京都の入札参加資格を取得すると、申請した営業種目ごとに「Aランク」「Bランク」「Cランク」というランクが付与されます。このランクのことを「等級」と言います。この等級は、「結果通知書」に記載されます。ですので、みなさんの会社が、東京都の入札参加資格を取得した際には、必ず「結果通知書」を東京都電子調達システムからダウンロードして、自分の会社の営業種目ごとの等級が「Aなのか?」「Bなのか?」「Cなのか?」確認をする必要があります。
また、東京都の入札参加資格を取得すると、有資格者名簿に掲載されます。自社の等級はもちろんのこと、同業や競合他社の等級を、東京都電子調達システムの有資格者名簿から確認することもできます。
(参考)「東京都電子調達システム>入札情報サービス>競争入札参加有資格者名簿」
そもそも、「A」「B」「C」という等級は、何のためにあるのですか?なんとなく「Cよりは、Aの方がよい」というのは理解できますが…
東京都の発注案件を見てもらうと分かると思うのですが、東京都は発注する案件ごとに、
(1)営業種目「116:映像等製作」に登録があり「A」等級に格付けされている者
(2)営業種目「120:催事関係業務」の「B」等級に格付けされていること
といった条件を付して、案件を発注しています。(1)の例でいうと、営業種目「116:映像等製作」の入札資格を持っていなければ、この案件の入札に参加できないのは、もちろんのこと、仮に「116:映像等製作」の入札資格を持っていたとしても、「B」や「C」の等級だった場合には、この案件の入札に参加することができません。
そして、「A」や「B」や「C」という格付けは、東京都が発注する案件の発注標準金額も、示しています。これは営業種目ごとに異なるので、正確な金額は手引きや公報を確認して頂きたいのですが、「事務用品や什器関係」の営業種目であれば「Aは、1000万円以上」「Bは、300万円以上1000万円未満」「Cは、300万円未満」というように発注標準金額が、グループ分けされています。
ですので、より金額の大きい入札に参加したければ、「C」よりも「B」、「B」よりも「A」を目指すべきだと言えます。
東京都の入札の「等級格付」の基準について
なるほど、金額の大きい入札に参加したいのであれば、「C」よりも「B」、「B」よりも「A」の方が有利というわけですね。では、この「A」「B」「C」という等級は、どうやって決まるのですか?
はい、この点については、資料を見ながら説明した方がわかりやすいと思いますので、資料を用意しました。おおまかな流れで言うと、客観点数から客観等級を算出し、主観点数から主観等級を算出します。そして、客観等級と主観等級が同一等級であれば、その等級が最終等級になり、客観等級と主観等級が一致しない場合には、より低い等級が、最終等級になるというルールがあります。
※添付の資料は、東京都が発行している手引の一部です。クリックすると、ページが拡大されます※
最終等級を算出するには、決算書が必ず必要になりますので、ぜひ、みなさんの会社の決算書を見ながら、数字をあてはめてみてください。
まずは、客観数値を算出します。
- 営業種目が「物品」の場合は、「年間総売上高」+「自己資本額」+「流動比率」+「営業年数」+「障害者雇用率」の数字の合計が客観数値になります。
- 営業種目が「委託」の場合は、「年間総売上高」+「自己資本額」+「「従業員数」+「流動比率」+「営業年数」+「障害者雇用率」の数字の合計が客観数値になります。
この計算によって算出した客観数値が
- 70点以上の場合、客観等級が「A」になり、
- 40点以上70点未満の場合、客観等級が「B」になり、
- 40点未満の場合、客観等級が「C」になります。
ここまでは大丈夫ですか?
はい。客観数値から客観等級の算出方法について、理解できました。

続いて、主観等級の算出方法についてです。主観等級は、主観数値から算出するのですが、「営業種目別の売上高」そのものが、主観数値になります。例えば、「営業種目005:荒物雑貨」の売上高が1000万円だった場合、「営業種目005:荒物雑貨」の主観数値は1000万点。「営業種目115:広告代理」の売上高が1億5000万円だった場合、「営業種目115:広告代理」の主観数値は1億5000万点となります。
この主観数値を先ほどの表にあてはめれば、主観等級を算出することができます。
「営業種目005:荒物雑貨」は、グループ2に属しますので、主観点数が1000万点の場合、主観等級はCになります。「営業種目115:広告代理」は、グループ5に属しますので、主観等級が1億5000万点の場合、主観等級はBになります。
主観等級は、営業種目ごとの売上高を主観数値に置き換えて、グループごとの表にあてはめて、算出するのですね。
はい。その通りです。
このような手順によって算出した客観等級と主観等級が、ともに同じ等級であれば、その等級が最終等級になります。たとえば、客観等級がB、主観等級もBという場合、最終等級もBになります。他方、客観等級と主観等級が同じ等級ではない場合、より低い方の等級が最終等級になります。たとえば、客観等級がA、主観等級がCという場合、最終等級はCになります。
「より低い等級が…」という点に注意する必要があります。
このようにして、最終等級を格付けしているのですね。ここで質問なのですが、「A」の方が有利ということであれば、何とかして「A」にするという方法はあるのですか?
とてもよい質問ですね。私のお客さまからも、同じような質問を受けることは、非常に多いです。たとえば、
- 「C」ではなく「A」がよい
- 「B」を「A」にしたい
というものです。しかし、「A」「B」「C」という等級は、あくまでも「客観数値を基準にした客観等級」および「主観数値を基準にした主観等級」から算出されますので、「Aがよいから…」という理由でAにすることはできないのです。
たとえば、客観数値を算出する際の基準になる「(イ)年間総売上高・(ロ)自己資本額・(二)流動比率」は、審査の際に提出する財務諸表が裏付資料となります。また、「(ホ)営業年数」は、同じく審査の際に提出する登記簿謄本が裏付資料となります。
こういった裏付資料とともに入札参加資格の申請を行うので、「A」「B」「C」という等級は、厳格に審査されていると考えてください。決して、自社の都合で、「Aが良いからAが取れる」というものではないことをきちんと理解しておく必要があります。
「等級の変更」について
それでは、一度は、「Cだった等級をBに変更する」というような、変更手続きは、できるのでしょうか?

いいえ。その点についても、よく質問を受けるのですが、資格の有効期間中、等級に関する変更は、認められないことになっています。仮に一度、C等級が確定した場合、少なくとも、その資格の有効期間中は「C等級のまま」ということになります。もちろん、年度が替わり、あらたな東京都の資格を申請する際には、その時の財務諸表の状況によって、等級が変更することはあります。しかし、資格の有効期間中は等級を変更することができませんので、この点についても、事前に頭の中に入れておく必要があります。
「等級の変更は、一切認められない」ということですね。なかなか厳しいですね。
たしかに変更が認められないのは、厳しいかもしれません。
ただ、東京都の発注案件を実際に見てみると、
- 「B」又は「C」の等級に格付けされていること
- 「A」又は「B」又は「C」の等級に格付けされていること
といったように、ある程度、幅を持って、案件が発注されるケースが見受けられます。このようなことを考えると、そこまで等級を気にする必要もないと思ったりもします。
また、たとえば、「A」が有利であるとは、一概に言い切れないケースもあります。たとえば先ほどの例のように、東京都が
- 「B」又は「C」の等級に格付けされていること
といった条件を付して案件を発注してきた場合、「B」や「C」の等級であれば、この案件の入札に参加できますが、「A」等級だと参加できなくなってしまいます。
あくまでも私の個人的な見解ですが、「絶対に、大きな案件を狙っていきたい」という強い希望がある場合を除いて、等級については、ありのままを受け入れるというスタンスでよいのではないかと思っています。
東京都入札参加資格の「無格付(X)」について
最後に1点、質問なのですが、「無格付(X)」という言葉を聞いたことがあります。この「無格付(X)」とは、どういった状況のことを言うのでしょうか?
東京都の入札参加資格を申請する上で、「無格付」の理解は、必須ですね。「無格付」とは、その名の通り、「格付が無いこと」を意味します。「A」「B」「C」という格付けが付かない状態です。
まず、前提として営業種目の売上高が、仮に「0円」であったとしても、入札参加資格を取得することは可能です。たとえば、とある会社の総売上高が1億円だったとします。その内訳は
- 印刷=8000万円
- 広告代理=2000万円
- 映像等製作=0万円
だったような場合。この会社は、「101:印刷」「115:広告代理」で入札参加資格を申請することができるのは、もちろんのこと、「116:映像等製作」でも東京都の入札参加資格を申請することができます。売り上げが0円であったとしても、入札参加資格を持つこと自体はできるわけです。
しかし、一方で、「売上高=0円」の「116:映像等製作」については、その会社の実績を判断することができないため、等級格付けが行われず、「A」「B」「C」のランクは付与されず、無格付(X)となってしまうのです。
売上高0円の営業種目があった場合、入札参加資格を持つことができても、その営業種目が「無格付(X)」になるのですね。
はい。その通りです。
「無格付」になると、東京都が積極的に指名を行うことはないので、入札に参加する機会が、著しく減ってしまうというデメリットがあります。「前年度の売上実績がない営業種目」「前年度の売上が0円の営業種目」については、『「無格付」になっても良いので、入札参加資格を取得するのか?』それとも『「無格付」だと入札資格を持っても意味がないので、申請しないのか?』判断が分かれるところであります。
入札参加資格を持っても、入札に参加できないのであれば、わざわざ申請する意味がないように思いますが、いかがですか?
私も同感です。
売上高が0円の営業種目については、入札参加資格を持つ意味は、とても低いでしょう。もちろん、念のために取得しておきたいというのであれば、構いませんが、弊所のお客さまに対して、私の方から、「取得しておいた方が良いですよ」というご案内はしておりません。
ありがとうございます。そろそろお時間になりましたので、最後に、一言お願いできますでしょうか?
今日お話したことは、すこし難しく感じたかもしれません。
『等級・格付』は、最初は難しそうに見えても、仕組みを理解すると、自社の状況に合った等級を事前に予測することができるため、これまで以上に受注の可能性が広がるチャンスでもあります。
わからないことがあれば、私たちのような専門家に相談することも選択肢のひとつです。
このインタビュー記事が、東京都の公共調達に挑戦しようとするみなさまが、一歩踏み出すきっかけになれば幸いです。