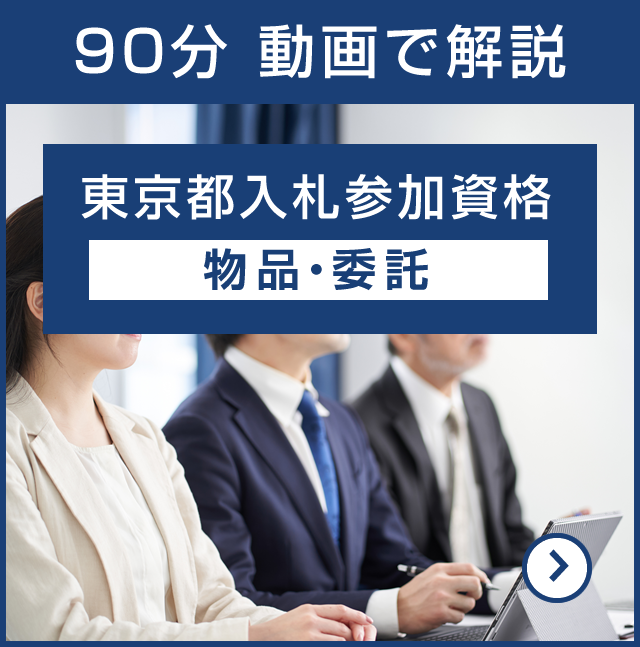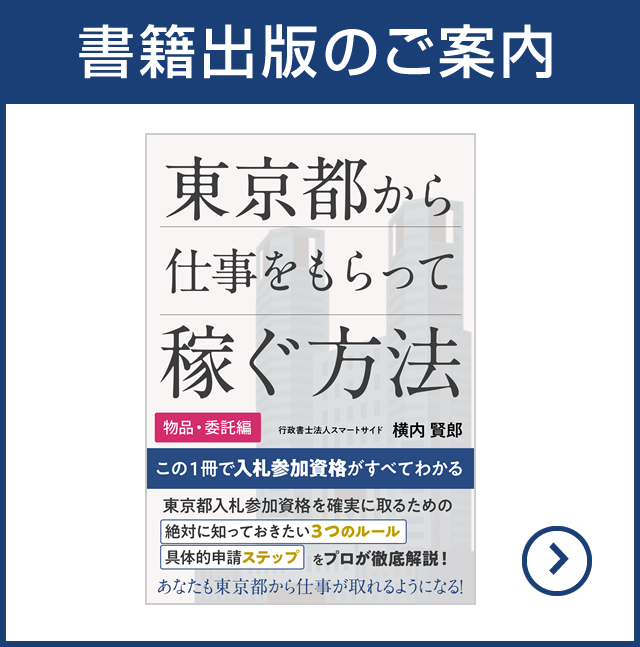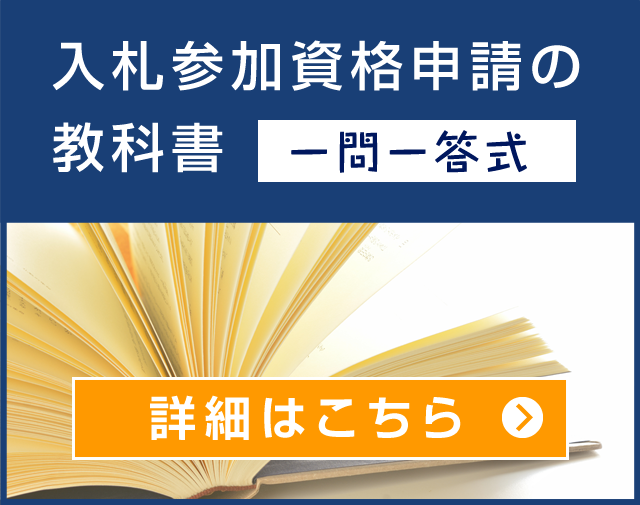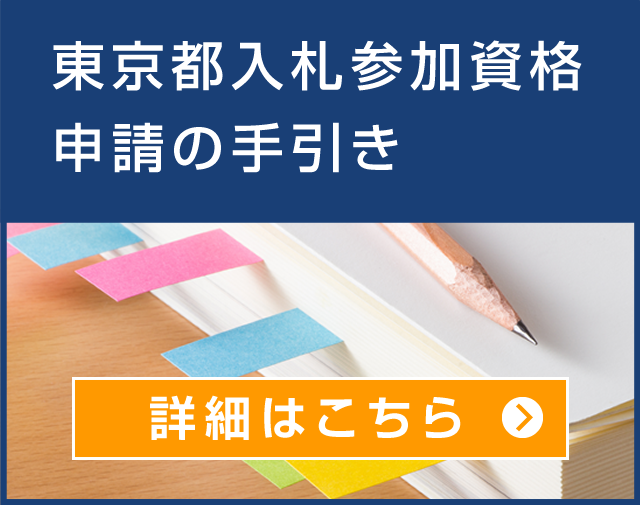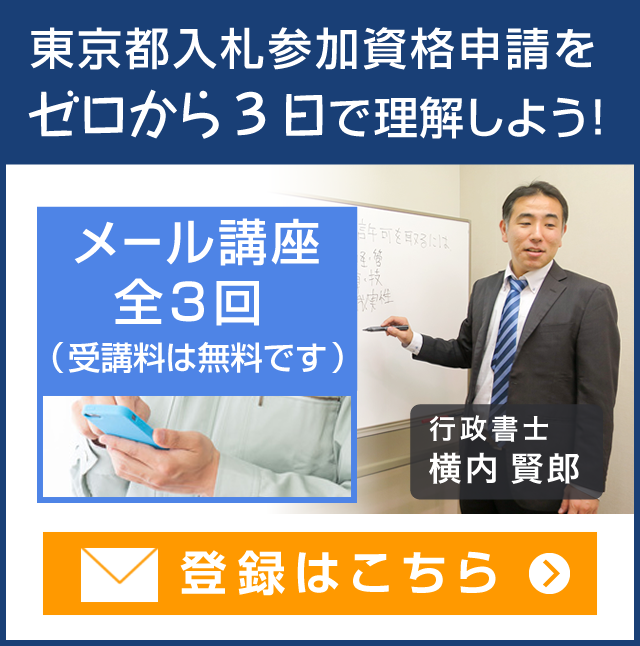行政書士法人スマートサイドは、東京都の入札参加資格申請(物品・委託)の専門家として、これまで数多くの事業者をサポートしてきた実績があります。
本インタビューでは、代表・横内賢郎が、申請をスムーズに進めるために押さえておきたい3つの重要ポイントについて解説。これから申請を予定されている社長・総務担当者にとって、不安を解消し、確実な手続きに繋がる内容となっています。
東京都入札参加資格申請を成功に導く3つの鉄則
それでは、横内先生、本日もよろしくお願いします。今日は、「東京都入札参加資格申請を成功に導く3つの鉄則」というテーマで、お話をお聞かせください。
こちらこそ、本日もよろしくお願いします。
東京都に限らない話ではありますが、入札参加資格を取得する手続きは、簡単ではありません。もちろん、マニュアルや手引きを読み込んで、時間をかけて1つ1つクリアしていくことによって、自分での申請ができないわけではありません。しかし、「素人の人が見よう見まねで申請をすると大きな落とし穴がある」という点について、できるだけわかりやすく、具体的に解説していきたいと思います。

承知しました。それでは3つの鉄則とは、具体的にどういったことを指すのですか?
あえて3つに絞ってお話ししますが、この3つが全てというわけではありません。ほかのインタビュー記事でお話ししているように、例えば「スケジュール管理」とか「電子証明書の取得」とか「等級の格付け」とかも大事です。とはいうものの、東京都の入札参加資格申請を初めてやろうとする人は、まずは、「営業種目・取扱品目」「売上高の割振り」「チェックリストへの入力」の3つについて、理解しておいて欲しいです。
以下では、順番にお話ししますね。
「営業種目・取扱品目」の決定について
ありがとうございます。まずは、「営業種目・取扱品目」についてですね。
はい。まずは、「営業種目・取扱品目」についてです。
東京都の物品・委託の入札参加資格は、全部で、67の営業種目に分かれています。物品は30の営業種目、委託等は37の営業種目です。この点については、弊所のホームページに詳細を記載していますので、興味のある人はぜひ、そちらを参考にしてみてください。
(参考)「東京都入札資格(物品)の営業種目・取扱品目の一覧」は、こちら
(参考)「東京都入札資格(委託)の営業種目・取扱品目の一覧」は、こちら
その「営業種目・取扱品目」ですが、最大で10個の営業種目、1営業種目につき8個の取扱品目を選択することができるようになっています。ただし、ここで注意しなければならないのは、一度選択した「営業種目・取扱品目」は、資格の有効期間中、変更・訂正・追加することができないという点です。
変更や追加が認められないのですか?
はい。一度、選択した営業種目や取扱品目は、資格の有効期間中、変更・訂正・追加をすることができません。これは、東京都が発行している手引にも明確に記載されていますので、自分で申請しようと考えている人は、絶対に押さえておく必要があります。
この点については、「何が問題になるのか?」よくわかっていない人もいると思うので、具体的に説明しますね。
例えば、みなさんの会社が「営業種目120」の「催事関係業務」の東京都の入札参加資格を取得したとします。しかし、実際に、入札案件を確認してみたら「営業種目120」の「催事関係業務」ではなく、「営業種目115」の「広告代理」で入札案件が発注されていたとします。この時に、みなさんの会社が「営業種目115:広告代理」で入札参加資格を持っていれば、この案件の入札に参加することができるのですが、もし「営業種目120:催事関係業務」しか入札資格を持っていなかったら、この案件には参加することができないのです。
「営業種目115:広告代理」を持っていないから当然です。
そこで、多くの人は、この入札案件に参加するために
- 「115:広告代理」の営業種目を後から追加したい
- 「120:催事関係業務」の営業種目を「115:広告代理」に変更したい
と考えるわけですが、東京都は、それを一切認めていないのです。
そうすると、入札参加資格を申請する際の「営業種目・取扱品目」の選択が、とても重要になるということですね。
はい。おっしゃる通りです。
資格の有効期間中での「変更・訂正・追加」が一切認められていない以上、営業種目や取扱品目の選択は、慎重に行うべきです。さっきの例で言うと、「営業種目115:広告代理」の入札資格を持っていさえすれば、少なくとも入札に参加することができたのに、それすらできなくなるのですから、ダメージは大きいと思います。
実際の案件を見て、「今から○○の営業種目を追加で申請することができますか?」という問い合わせが非常に多いです。そういったことは、できないルールになっているので、事前に要チェックしておいて欲しいです。
「売上高の割振り」について
そういったルールがあったのですね。これは、事前に聞いておいてよかったと思います。それでは、2つめの鉄則は何でしょう。
2つ目の鉄則は、「売上高の割振り」についてです。
先ほどの、「営業種目・取扱品目」の選択と関連しますが、東京都に入札参加資格を申請する際には、「営業種目・取扱品目」ごとに、売上高の割振りを行わなければなりません。

例えば、みなさんの会社の前期の売上高が1億円だった場合。
- 002:事務機器・情報処理用機器
- 005:荒物雑貨
- 026:警察・消防・防災用品
の3つの営業種目を選択するとします。
東京都に入札参加資格を申請する際、1億円の売上高を営業種目ごとに割り振る必要があります。割振りの根拠となる裏付け資料の提出までは、求められていないので、比較的ざっくりと「002は20%、005は30%、026は50%」というように、金額を割り振って申請している例も見られます。しかし、ここで注意しなければならないのは、営業種目ごとの売上高が、等級格付けに直結していることと、売上高0円は無格付け(X)になるということです。
「等級の格付け?」「無格付け?」、ちょっと聞き慣れない言葉が多くて、難しく感じます。もう少し、わかりやすく説明していただけますでしょうか?
この点は、難しく感じる人が多いため、すこし、丁寧に説明します。
まず、「等級の格付け」についてです。
東京都の入札参加資格を申請すると、申請した営業種目ごとに「A・B・C」というランクが付与されます。このランクのことを「等級」といい「等級」を決定することを「等級の格付け」といいます。みなさんもご存知かもしれませんが、等級は、CよりもBの方がよく、BよりもAの方がよいという関係性になっています。そのため、金額の大きい入札に参加したいのであれば、CランクよりもAランクを持っている方が有利です。
この格付けは、先ほどの営業種目の売上高で決まってきます。「営業種目の売上高が全て」というわけではないのですが、「営業種目の売上高」が低いと、ランクも低くなるという相関関係があるのです。そのため、万が一でも、間違った数字(金額)を入力してしまうと、間違った格付けを行われてしまうというリスクがあります。
たとえば、「026:警察・消防・防災用品」の売上高が5000万円だった場合、Aランクが付与される可能性があります。しかし、何らかの手違いで「026:警察・消防・防災用品」の売上高を500万円と入力してしまった場合、格付けは良くてもBランクどまりとなってしまいます。
このように、東京都の入札参加資格を申請するとA・B・Cという等級が付与されて、その等級に応じて発注予定価格の金額や入札の規模感がグループわけされています。その等級の格付けは、営業種目ごとの売上高を基準に決定されていることを覚えておいてください。
この点については、非常に難しいところでもありますので、より深く知りたいとか事前に等級を確認したいという人は、弊所の事前予約制の有料相談サービスをお申込みください。
「等級の格付け」については、理解できたような気がしますが、「無格付け」とは何なのですか?
はい。
「無格付け」は(X)とも表記されるのですが、単純に言うと「A」「B」「C」というランクをつけることができない状態のことを言います。営業種目の売上高を0円として申請すると「無格付け」になります。
例えば、先ほどの例でいうと、「005:荒物雑貨」の前期の売上高が0円だったとすると「005:荒物雑貨」の等級は「無格付け(X)」ということになります。この「無格付け」の問題点は、「無格付け」になると、ほとんど入札に参加することができないという点にあります。
入札参加資格を持っているのに、入札に参加できないのですか?
はい。正確に言うと、「無格付け」の場合、入札参加資格を持っているのに、入札に参加できる機会が制限されるといったほうが良いかもしれません。
これは、東京都の手引きにも明確に記載されていることですが「審査対象事業年度の売上高が0円であっても申請は可能です。ただし、申請営業種目内の全ての取扱品目の売上高を0千円で申請されますと、当該営業種目は無格付となり、入札参加できる案件が極めて限定されますので、ご了解ください。」とあります。
もう少し簡単に言うと、前期の売上高が0円の営業種目でも入札参加資格を取得すること自体はできるのですが、その場合、当該営業種目に対する販売能力を判断することができないため、「無格付け」となり、東京都が積極的に入札参加指名を行うことがないのです。
なるほど、「営業種目の売上高が0円、イコール、無格付け。そして、無格付けの場合、ほとんど入札に参加することができない」ということですね。
はい、そういう理解であっています。
しかも、「営業種目・取扱品目」と同様に、後になってから営業種目の売上高を変更・訂正することができません。つまり、万が一、なんらかの手違いで0円で申請してしまうと、入札資格は持てても、入札に参加することが「ほぼ無理」ということになってしまうのです。
売上高の割振りが大事なことが、お分かりいただけましたか?
東京都社会的責任調達指針(チェックリスト)について
よくわかりました。それでは、最後に挙げられた「チェックリストへの入力」とは、具体的にどういったことを指すのでしょうか?

このチェックリストへの入力は、令和7年から始まった比較的新しい入力項目です。正確には「東京都社会的責任調達指針に関するチェックリスト」と言いますが、このチェックリストへの入力に手こずっているお客さまが非常に多いように思います。
この点については、私が口頭で説明するよりも、東京都社会的責任調達指針のホームぺージを見ていただいた方が早いと思いますが、要は、「環境」「人権」「労働」「経済」の各分野で持続可能性のある取組を行っている会社を優遇していこうという制度です。
いまのところチェックリストへの入力内容が、資格審査に影響することはないと明示されています。そのため、等級の格付けについて、有利不利ということはありません。しかし、一方で、「義務」と書かれている項目について「取り組んでいない」を選択すると、調達指針が適用される案件には参加することができなくなるというリスクもあるようです。
具体的にどういった内容の項目があるかというと、「環境」については
- 温室効果ガス排出量の特定、削減のための措置
- 再生可能エネルギーに由来する電気や熱等、CO2排出係数のより低いエネルギーの利用
- 省エネルギー効果の高い設備や物流の導入等による消費エネルギーの低減
などが、「人権」については
- 人種・宗教・性別・障害の有無等による、いかなる不当な差別やハラスメントも防止すること
- 障害者への不当な差別的取り扱いの防止、合理的配慮の提供
- 社会的少数者が平等な経済的・社会的権利を享受するための支援
など、50以上の項目が掲げられています。
先ほど、お伝えしたように等級の格付けについては、影響しませんが、入力項目が50以上あり、時間がかかってしまう傾向にあるので、申請手続きに入る前に、事前にチェックリストの中身を確認しておくことをお勧めいたします。「東京都社会的責任調達指針に関するチェックリスト」は、申請手続きの入力画面の一番最後に用意されており、しかも、このチェックリストへの入力が完了しないと、申請ボタンに進むことができない仕様になっていますので、ご注意ください。
「東京都社会的責任調達指針に関するチェックリスト」なるものがあるのですね。はじめて知りました。等級格付けに影響はないとは言え、自社の人権や環境への配慮を今一度、確認しておいた方がよさそうです。それでは、お時間になりましたので、最後に一言お願いいたします。
今日、お話ししたことは、東京都の入札参加資格申請に関する注意事項のうち、ほんの一部にすぎません。「3つの鉄則」ということで「営業種目・取扱品目」「売上高の割振り」「チェックリスト」について、初めての人でも分かるように説明したつもりですが、いかがでしたでしょうか?
行政書士法人スマートサイドは、入札参加資格申請の専門家として、東京都や省庁への申請を得意としています。特に東京都の入札参加資格は東京都電子調達システムを利用しなければならず、事前に電子証明書やICカードリーダが必要な点において、難しい手続きということができます。しかも「等級」「格付け」「発注標準金額」などについても、調べだすとなかなか難しいことに気づくと思います。
弊所では、東京都の入札参加資格の取得で、困っていることや不安・疑問を解消したいという人のために、事前予約制の有料相談も実施しています。この有料相談では、みなさんの会社の個別の事情に合わせて「スケジュール管理」や「電子証明書の取得」や「等級の格付け」についてもご案内させていただくことが可能です。
もし、今日のインタビュー記事を読んで、もう少し、「深く知りたい」「疑問を解消したい」と言う人がいれば、ぜひ、事前予約制の有料相談をお申し込みください。それでは、本日は、長時間にわたって、ご清聴いただきありがとうございました。