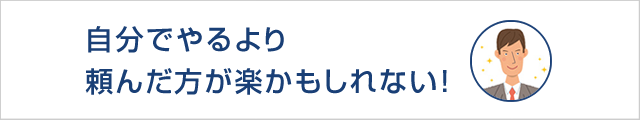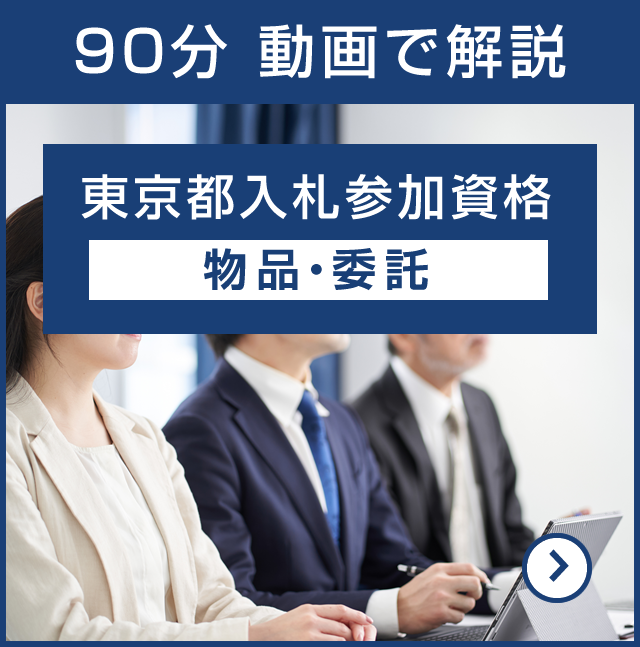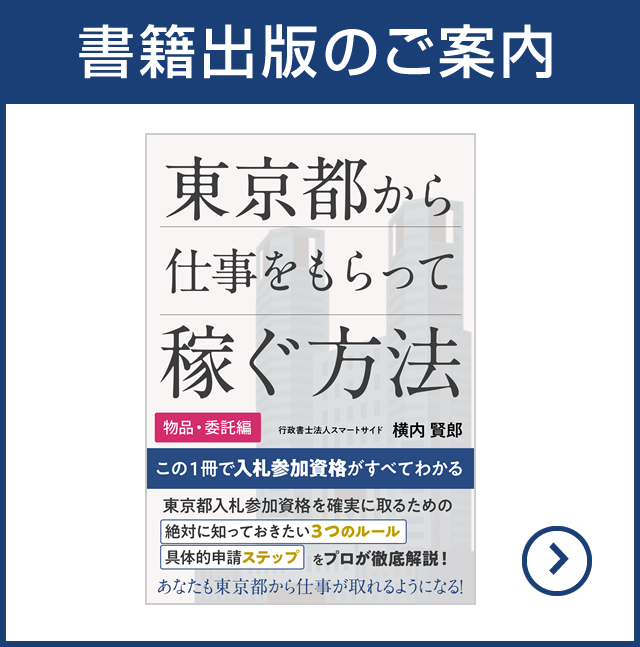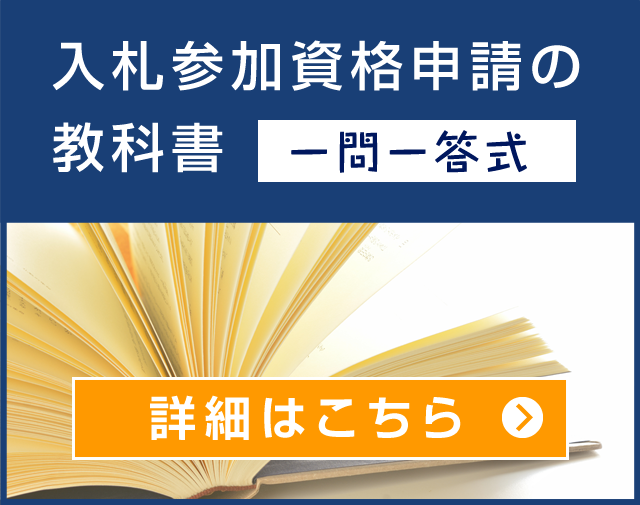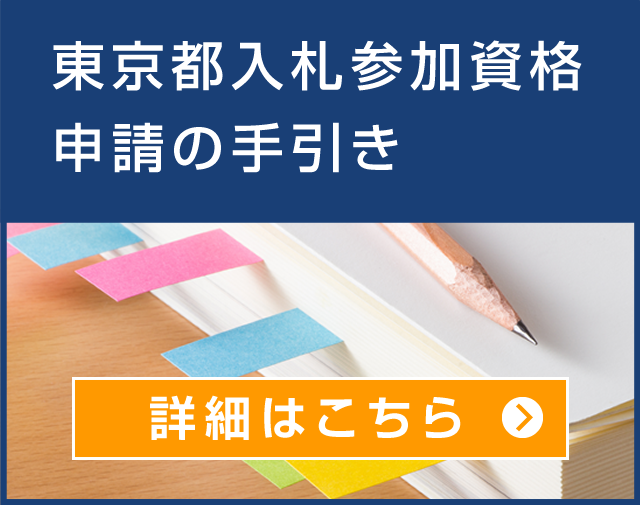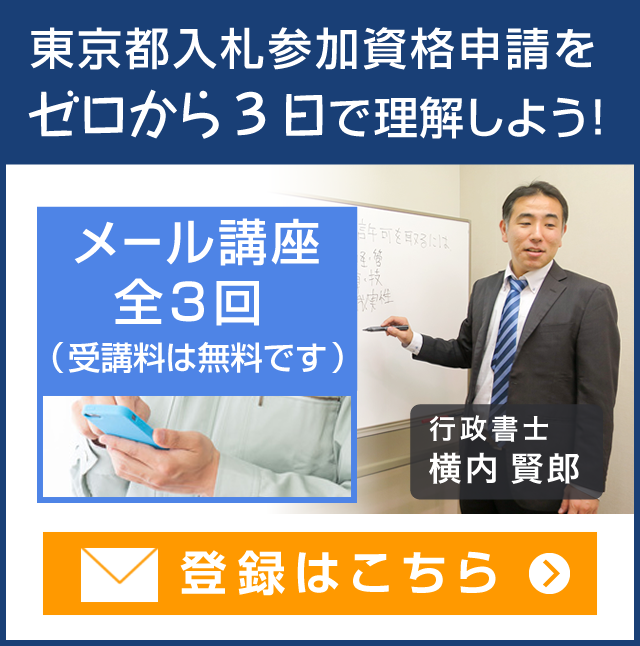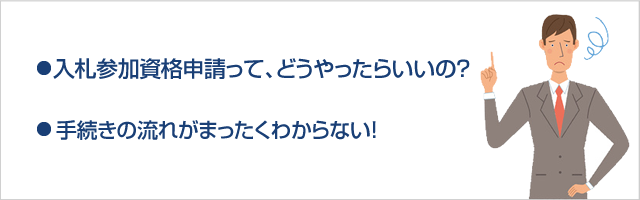
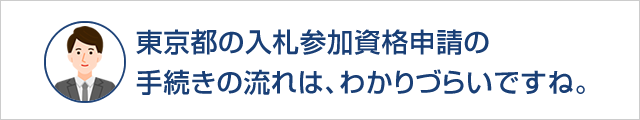
「東京都の入札参加資格申請の手続きの流れ」については、分かりづらくてお困りの事業者さまが多いようです。東京都の入札参加資格を取得するには、「データを打ち込んで、電子申請をすること」が必要ですが、それだけではありません。
まずは、電子証明書・ICカードリーダの取得から始まって、パソコンの設定、システムのインストールを経て、はじめて資格申請にたどり着くことができます。資格申請後にも、必要書類の電子送付・承認通知の受取、資格通知書のプリントアウトなどやることは盛りだくさんです。
このページでは、東京都の入札参加資格を取得するための手順について理解できず苦労されている方のために「行政書士法人スマートサイドにご依頼頂いた際の手続きの流れ」について、説明をさせて頂きます。
| 【手続きの流れ】 | 【項目】 |
|---|---|
| 0.事前相談、事前打ち合わせ |
ご要望に応じて |
| 1.電子証明書取得のための事前準備 |
|
| 2.電子証明書取得手続き |
|
| 3.パソコンの設定手続き |
|
| 4.電子申請+必要書類の電子送付 |
|
| 5.入札参加資格申請の承認 | 申請後1~2週間程度 |
| 6.入札参加資格の適用+名簿登載 | おおむね承認の翌月1日~ |
入札参加資格申請の手続きの流れ

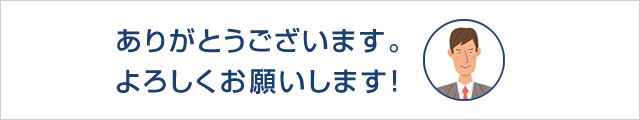
行政書士法人スマートサイドに、ご依頼頂いた際には、以下の「0~6」の手続きの流れを経ることによって、東京都(都内区市町村)の入札参加資格を取得することができます。
0.事前相談・事前打ち合わせ
- はじめてなので、実際に会って話を聞きたい…
- 手続きの流れを詳細に確認したい…
- 質問事項や確認事項があるので、事前に相談させて欲しい…
という方のために、有料(11000円/1時間程度)の事前相談・事前打ち合わせを行います。事前相談・事前打ち合わせは、任意ですので、ご希望の方は、あらかじめその旨、お伝えください。
1.電子証明書を取得するための事前準備
まずは、入札参加資格を電子申請する際に必要な「電子証明書+ICカードリーダ」を取得するための事前準備の手続きです。
1-1:住民票・印鑑証明書などの取得
電子証明書+ICカードリーダを取得するには
- カード名義人(通常は代表者)の住民票
- カード名義人(通常は代表者)の印鑑証明書
- 会社の印鑑証明書
- 直近の財務諸表
が必要ですので、まずは、上記書類のご準備をお願いします。
1-2:電子証明書購入申込書・委任状などへの押印
上記書類がそろったら、弊所にご郵送ください。御社から、上記書類が届き次第
- 電子証明書購入申込書
- Aosignサービス委任状
といった、電子証明書を購入するために必要な書類の作成を行います。
弊所で作成した1.2の書類は、メールにて御社に送信しますので、該当箇所に指定の印鑑(実印、代表者印など)を押印後、弊所に郵送して頂きます。
1-3:申請に必要な事項のヒアリング
「1-2:電子証明書購入申込・委任状などへの押印」作業と、並行して、申請に必要な事項のヒアリングも添付して送信します。
- 御社の営業種目
- 電子証明書の有効期間
など、をご回答ください。
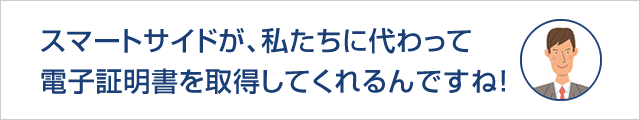
2.電子証明書取得手続き
御社から押印済みの「1.電子証明書購入申込書」「2.Aosignサービス委任状」が届き次第、日本電子認証(株)に電子証明購入申込手続きを行います。
2-1:電子証明書・ICカードリーダの取得
電子証明書+ICカードリーダは、弊所が受取代理人として、御社に代わって受領します。電子証明書は、本人限定受取郵便で発行されますが、弊所が受取代理人になっていますので、
- 社長が郵便局まで受け取りに行く
- 社長が日本電子認証(株)まで受け取りに行く
といった手間を省くことができます。
2-2:PINの受領
電子証明証明書を使用する際の暗証番号(PINの通知)は、簡易書留で社長の「住民票上の住所」に届きます。
この暗証番号(PIN番号)は、電子申請の際はもちろんのこと、電子入札の際にも必ず必要になってきますので、なくさないように厳重に保管しておいてください。
3.パソコンの設定手続き
「電子証明書+ICカードリーダ+PIN番号」の3点がそろったら、御社のパソコンで「電子証明書」「ICカードリーダ」「東京都の電子調達システム」を使えるようにする必要があります。
下記3点のいずれも、実際に御社に伺って、パソコンの設定を行います。
3-1:環境設定+動作確認
「電子証明書」「ICカードリーダ」を使用するのに必要なソフトのインストールを行います。インストールが完了したことを確認するために、実際に「電子証明書」「ICカードリーダ」「PIN番号」を用いて、動作確認を行います。
3-2:電子証明書の登録
東京都の入札の場合には「東京都電子調達システム」、都内区市町村の入札の場合には「東京電子自治体共同運営サービス」に、電子証明書の登録手続きを行います。
3-3:行政書士への委任手続き
「3-1」「3-2」に続けて、御社のパソコン上で「3-3:行政書士への委任手続き」を行います。「行政書士への委任手続き」を行うことによって、御社のパソコンから…ではなく、弊所のパソコンを利用して、入札参加資格の電子申請を行うことができるようになります。
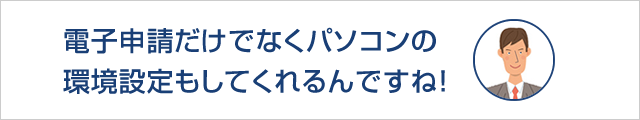
4.電子申請+必要書類の電子送付
ここからが実際の電子申請手続きの始まりです。
4-1:入札参加資格の電子申請
「営業種目・取扱品目、過去の実績、保有資格など…」さまざまな入力項目がありますので、その入力項目をすべて間違いなく入力したうえで、弊所のパソコンから御社に代わって電子申請を行います。
4-2:必要書類の電子送付
- 登記簿謄本
- 財務諸表(貸借対照表、損益計算書など…)
を電子送付する必要があります。なお、都内区市町村への入札参加資格申請を行うには、上記に加えて
- 法人事業税納税証明書
- 法人税納税証明書
- 消費税納税証明書
が必要になります。登記簿謄本および納税証明書(3通)は、御社に代わって弊所が代理で取得し、必要書類として受付窓口に郵送いたします。
5.入札参加資格申請の承認
「4-1:入札参加資格の電子申請」および「4-2:必要書類の郵送」が完了すれば、あとは、入札参加資格の承認通知を待つだけです。電子申請や必要書類に不備があると、否承認となり、申請をやり直したり、追加書類を郵送する必要があります。
6.入札参加資格の適用+名簿登載
入札参加資格が承認されれば、入札に参加することができるようになります(入札参加資格の適用)。入札参加資格が適用されると、都庁のホームページ上にある入札参加資格者の名簿一覧に、御社の「商号」「所在地」「代表者氏名」「営業種目」などの情報が掲載されることになります。
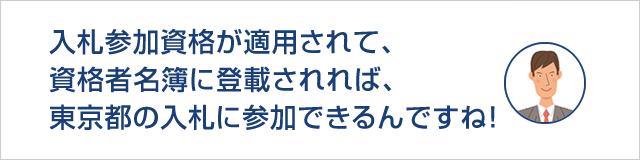
入札参加資格申請がよくわからないという方は…
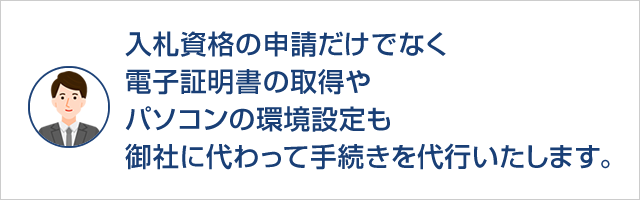
「入札参加資格申請って、どうもよくわからない」と感じる方は、多いですね。
入札参加資格申請といっても、「全省庁統一資格」「東京都」「東京23区市町村」「その他の県や市」などといったように自治体の数だけ申請の種類があるわけです。しかも、「全省庁統一資格」の有効期限は3年、「東京都」は2年、「東京23区市町村」は1年8カ月といったように資格の有効期間が異なります。また、定期受付・随時受付どっちに申請すればよいのか?申請先はどこなのか?いつから資格を持つことができるのか?についても、全く異なってきます。
さらに、電子証明書の準備は、東京都や区市町村といった役所とやりとりするわけではなく、「コアシステム対応認証局」といった聞きなれないところとやりとりをすることになります。
さて、これだけのことを事前に調べて自社で処理しようとなると、時間がいくらあっても足りませんね。また、万が一、「間違えてしまった」「申請期限に間に合わなかった」などという事態になってしまったら、せっかくの苦労も水の泡ですね。
このような「自分でやれば、やれなくもないけれど、その為に費やす時間と労力がもったいない事」に関しては、申請のプロフェッショナルである行政書士に外注してみてはいかがでしょうか?
申込書を書いたり、電子証明書を郵便局まで取りにいったり、登記簿謄本を法務局まで取りにいったり、パソコンの設定を時間をかけておこなったり・・・やり慣れない、面倒なことは、すべて行政書士法人スマートサイドにお任せいただいて、御社は本業に専念してください。