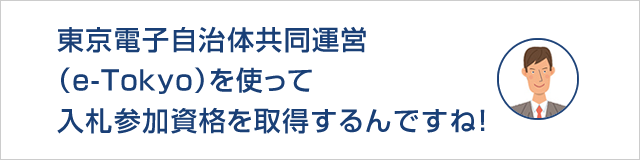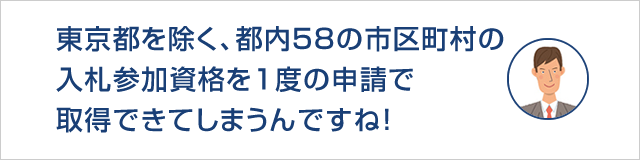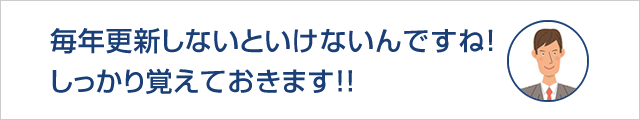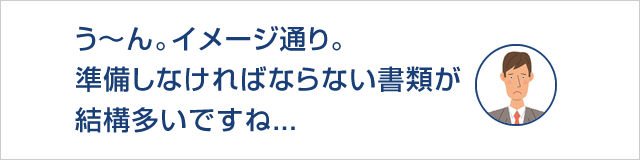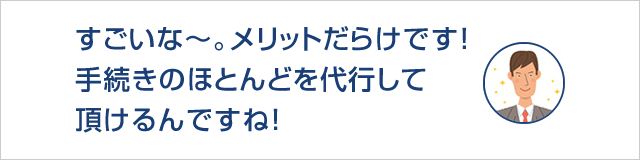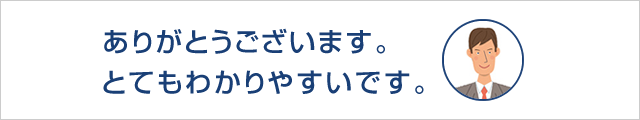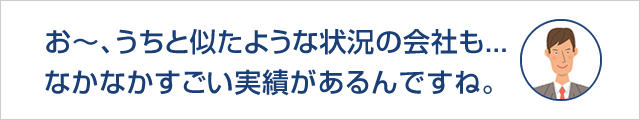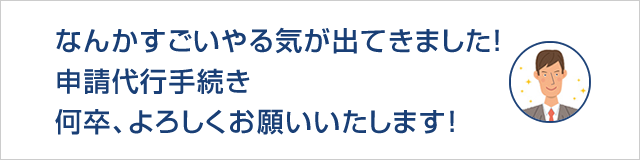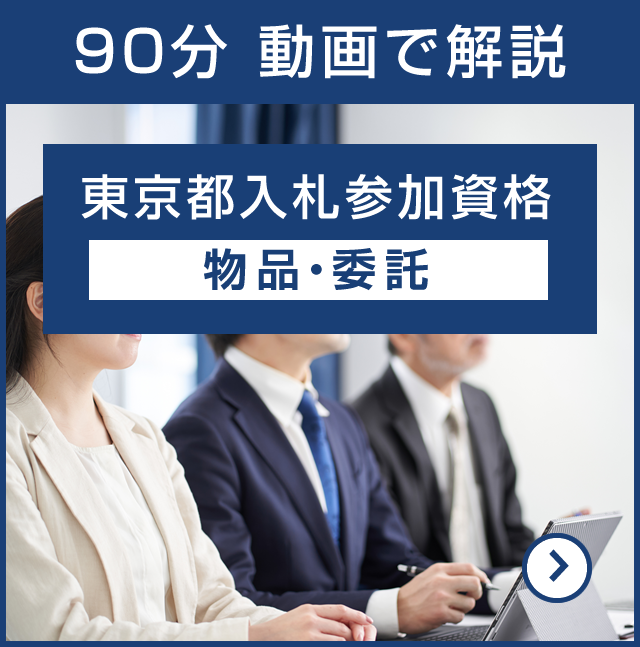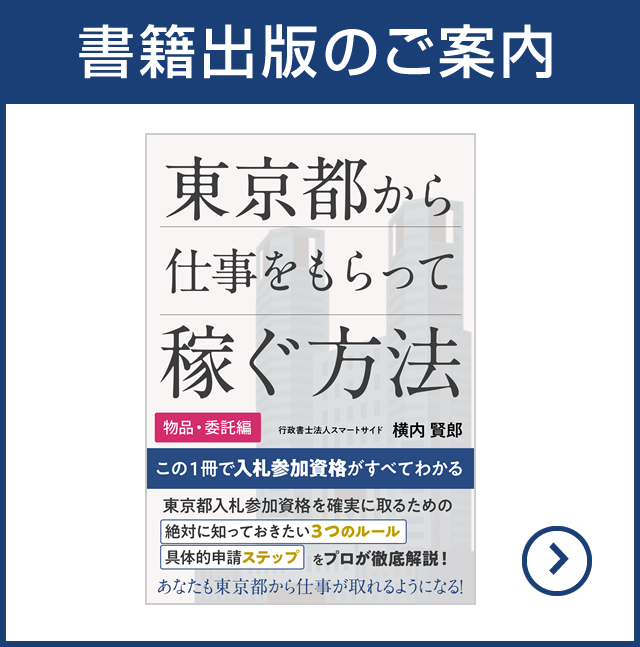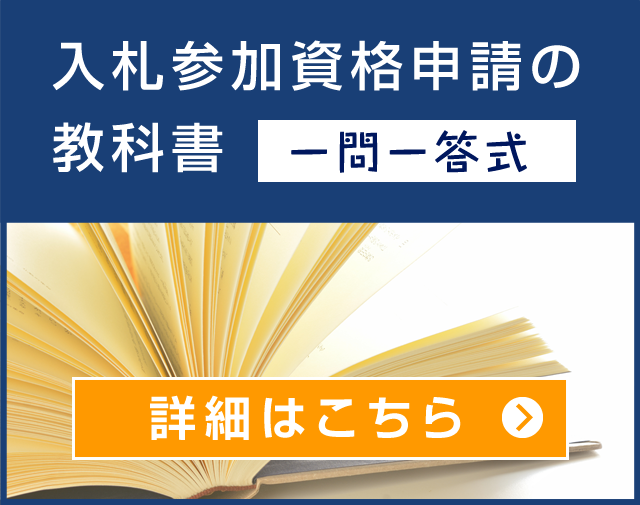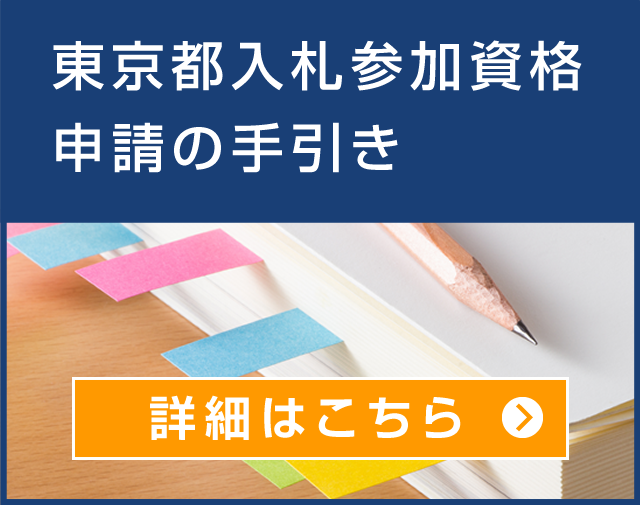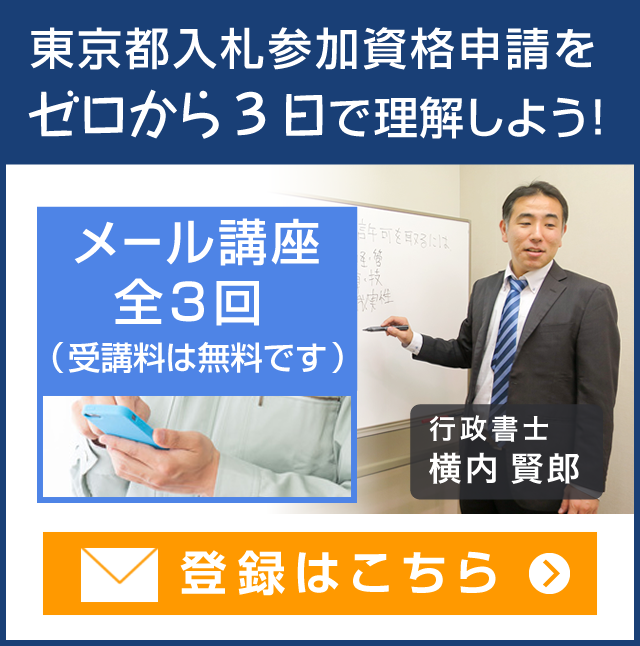このページは、東京都内の区や市の入札に参加したい方のために記載したページです。「中央区」や「港区」といった東京都下の自治体の入札のルールや「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス(e-Tokyo)」といった電子入札システムを理解して、「東京都内23区市町村」の入札参加資格を取得しましょう!
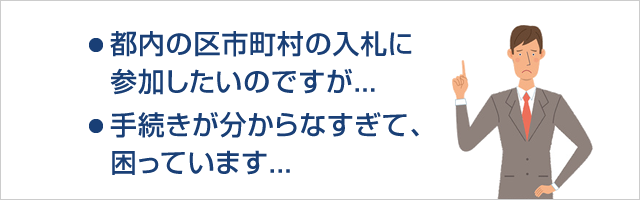
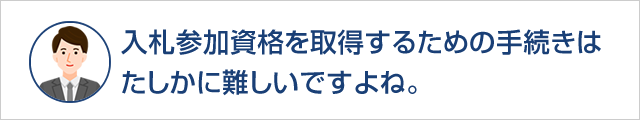
- 江東区、港区、台東区といった、東京都内の特別区の入札に参加したい
- 立川市、三鷹市、小平市といった、東京都内の市の入札に参加したい
- 東京電子自治体共同運営サービス?e-Tokyo?って何?
- そもそも、入札に参加するための資格を取得するための手続きが、さっぱりわからない?
- 役所の人に聞いても、なんだかよくわからなかった!
ということで、お困りの方はいらっしゃいませんか?
みなさんが「わからない」「困っている」というのも無理ありません。というのも、都内区市町村の入札に参加するには「入札参加資格申請(電子申請)」という特別な手続きを経たうえで、都内区市町村の入札参加資格を取得する必要があります。
この手続きは「だれでも簡単にできる」ような、やさしい手続きではありません。むしろ、行政書士資格を持っている人たちでさえ、きちんと理解できている人は少数です。
そこで、このページでは、入札参加資格申請の専門家である行政書士法人スマートサイドが、東京都内の「区」や「市」の入札参加資格申請について、徹底的にわかりやすく解説させて頂きます。
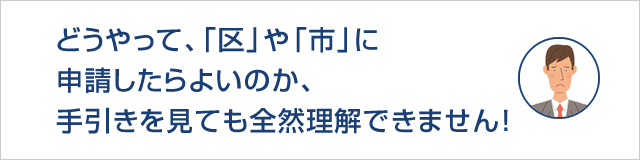
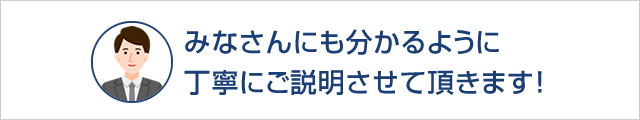
| 専門家による区市町村入札ガイド | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【1】 | 東京電子自治体共同運営 電子調達サービス(e-Tokyo)とは | ||||||
| 【2】 | 東京都内区市町村:入札の適用範囲 | ||||||
| 【3】 | 東京都内区市町村:入札の有効期間 | ||||||
| 【4】 | 東京都内区市町村:入札資格の取得手続きの流れ | ||||||
| 【5】 | 東京都内区市町村:入札資格を取得するための必要書類 | ||||||
| 【6】 | 行政書士法人スマートサイドに依頼する6つのメリット | ||||||
| 【7】 | 東京都内区市町村:入札資格取得のための期間と費用 | ||||||
| 【8】 | 東京都内区市町村:入札資格取得の成功事例のご紹介 | ||||||
| 【9】 | 東京都内区市町村の入札に参加したいとお考えの方へ | ||||||
東京電子自治体共同運営 電子調達サービス(e-Tokyo)とは
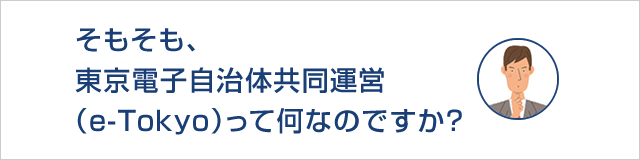
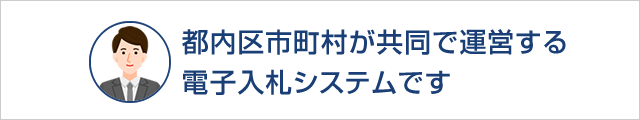
手引きやマニュアルを見ても、「聞いたことのない言葉」「はじめて見る単語」が、多くて、先に進めない方もいらっしゃるかと思います。いきなり横文字で「イートーキョー」と言われれも「なんのこっちゃ」となるのも無理はありません。
そこで、まず初めに、東京都内の区や市の入札資格を取得する際に必要な「東京電子自治体共同運営電子調達サービス(e-Tokyo)」について理解していくことにしましょう。
東京電子自治体共同運営 電子調達サービス(e-Tokyo)
東京電子自治体共同運営 電子調達サービス(以下「e-Tokyo」と省略)とは、東京都内の区市町村の入札に関するインターネット上のシステムのことを言います。
「入札参加資格を取得」はもちろんのこと「入札参加のための希望申請」や「案件落札の通知」といった入札に関するほとんどのことを、この「e-Tokyo」を使っておこなうことになります。
昔は、紙で行っていた入札参加資格の申請・入札の通知・札入れ・案件落札などの手続きを、すべてまとめてインターネット上でできるようにしたのが「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス=e-Tokyo」です。
東京都電子調達システム
これに対して「東京都電子調達システム」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
この「東京都電子調達システム」は「東京都」の入札に参加するためのインターネット上のシステムです。入札の電子申請に関するシステムという意味では「e-Tokyo」と同じですが、東京都なのか?東京都内の区市町村なのか?といった点で違いがあります。
| e-Tokyo(東京電子自治体共同運営) | 都内区市町村の入札に関するシステム |
|---|---|
| 東京都電子調達システム | 東京都の入札に関するシステム |
といったように、2つを分けて理解するようにしてください。
東京都内区市町村:入札の適用範囲
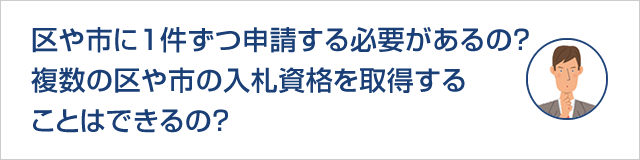
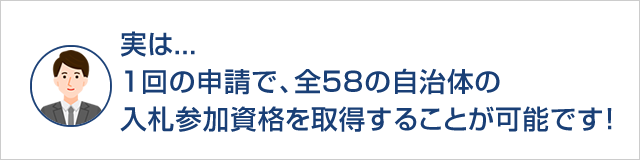
「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス(e-Tokyo)」を利用して申請手続きを行うと、「どの自治体」「どの区」「どの市」の入札に参加することができるようになるのか?は、とても重要です。
複数の区や市の入札に参加することができるようになるのか?東京都の入札に参加することができるのか?といった点について、説明して行きます。
区市町村を含む東京都内全59の自治体
「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス(e-Tokyo)」を利用することによって「入札参加資格」を取得することができるのは、以下の59の自治体です。東京都下のほとんどの市区町村を網羅しているはずです(※令和5年7月に「多摩ニュータウン環境組合」が加わり全59の自治体への申請が可能になりました)。
| 千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 |
| 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 | 目黒区 |
| 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 |
中野区 |
杉並区 |
| 豊島区 | 北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 |
| 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 |
| 武蔵野市 | 三鷹市 | 青梅市 | 府中市 | 昭島市 |
| 調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 日野市 |
| 東村山市 | 国分寺市 | 国立市 | 福生市 | 狛江市 |
| 東大和市 | 清瀬市 | 東久留米市 | 武蔵村山市 | 多摩市 |
| 稲城市 | 羽村市 |
あきる野市 |
西東京市 | 瑞穂町 |
| 日の出町 | 檜原村 | 奥多摩町 | 八丈町 | 青ヶ島村 |
| 小笠原村 | 多摩川衛生組合 | 二十三区清掃一部事務組合 | ||
| 多摩ニュータウン環境組合 | ||||
注目すべきは、1回の申請で全59の自治体の入札参加資格を取得することができるといった点です。
もちろん、目当ての区や市を選んだうえで、
- 本店所在地がある「荒川区」のみ
- 本社の住所と隣接している「杉並区」「練馬区」「世田谷区」
- 23区を除いた「市」のみ
といった申請の仕方をすることもできます。
しかし、1回の申請で全59の自治体の資格を取得することができるため、特にこだわりがなければ、全59の自治体を選択して申請することをお勧めいたします。
東京都の入札に参加できるのか?
では、「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス(e-Tokyo)」を利用して「東京都」の入札参加資格を取得することはできるのでしょうか?
この点については、注意してください。
先ほど説明したように
- e-Tokyo:東京都内区市町村に入札に関するシステム
- 東京都電子調達システム:東京都の入札に関するシステム
でした。
そのため、「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス(e-Tokyo)」を利用して「東京都内区市町村(全58か所)」の自治体の入札参加資格を取得することはできても、「東京都」の入札参加資格を取得することはできません。
「東京都」の入札参加資格を取得するには「東京都電子調達システム」を利用して、別途、申請手続きをしなければなりません。
東京都内区市町村:入札の有効期間
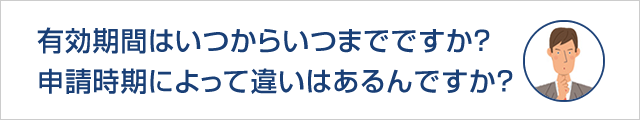

では、「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス(e-Tokyo)」を利用して取得した「東京都内区市町村」の入札参加資格は、いつからいつまで有効なのでしょうか?
この有効期限を把握しておかないと、いつの間にか入札参加資格を喪失していて「いざ、入札に参加しよう!」と思った段階で、「入札に参加することができない…」といった事態にもなりかねませんので、事前に確認しておくことが必要です。
資格の適用日
まず有効期間について検討する前提として「資格の適用日」を知る必要があります。この「資格の適用日」とは、「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス(e-Tokyo)」を利用して「東京都内区市町村」の入札参加資格を取得した場合、いつから都内区市町村の入札に参加できるのか?といった日にちを指します。
この資格の適用日については、以下のように、「翌月の1日から」もしくは「翌々月の1日から」となっています。
| 承認日 | 資格適用年月日 |
|---|---|
| 毎月1~25日までに承認された場合 | 翌月1日~の資格適用 |
| 毎月26日~末日までに承認された場合 | 翌々月1日~の資格適用 |
資格の有効期間
「東京都内区市町村」の入札参加資格は、直前の確定した決算の翌月から起算して、1年8か月の間、有効です。
このため、東京都の入札参加資格であれば2年度ごとの更新が必要で、全省庁統一資格(全省庁の入札資格)であれば3年度ごとの更新が必要なのに対して、東京都内区市町村は1年ごとの更新(継続申請)が必要になります。
では、なぜ1年8か月という中途半端な数字なのでしょうか?後述しますが、「東京都内区市町村」の入札参加資格の取得には、納税証明書の添付が必要になります。
そして、納税などの税務申告は、決算を迎えて2か月以内に行うのが通常です。そこから6か月間の時間的な余裕を持たせた結果、有効期間は1年8か月になったというわけです。
有効期間を具体的に見ていくと
たとえば、3月末決算の会社の場合、「東京都内区市町村の入札参加資格の有効期間」は、翌年の11月末になります。翌年の3月末に決算を迎えて、5月末までに各種納税申告を済ませて、その6か月後の11月末までに、更新(継続申請)を行わなければなりません。
では、12月末決算の会社の場合は、どうでしょう?12月末決算の会社の場合、「東京都内区市町村の入札参加資格の有効期間」は翌々年の8月です。この場合、翌年12月末に決算を迎えて、翌々年2月末までに納税などの申告を済ませ、その6か月後である翌々年8月までに更新(継続申請)を行わなければなりません。
何はともあれ、「東京都内区市町村の入札参加資格の有効期間」は、東京都のような2年でもなければ、全省庁統一資格のような3年でもなく、1年8か月なわけですから、入札参加資格を継続する以上は、毎年毎年決算期後6か月以内に更新のための継続申請を行う必要があると覚えておいてください。
東京都内区市町村:入札資格の取得手続きの流れ
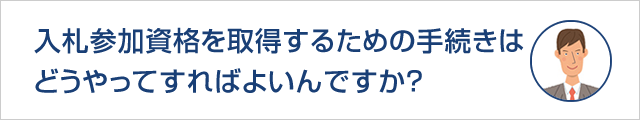
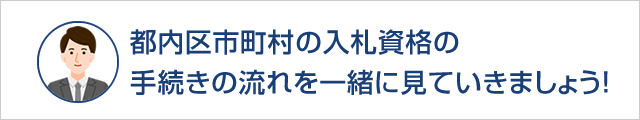
「東京都内区市町村の入札参加資格」を取得するには、その手続きの流れを理解することが必須です。ですが、この手続きの流れを理解するのが一番わかりづらいといったも過言ではありません。
そこで、ここでは、手続きを細分化し
- 電子証明書+ICカードリーダを取得するための手続き
- パソコンの入札環境を設定するための手続き
- e-Tokyoを利用した電子申請手続き
の順番で見ていくことにしましょう。
1.電子証明書・ICカードリーダ取得のための手続き
まず前提として「東京都内区市町村の入札参加資格」を取得するためには、「電子証明書+ICカードリーダ」を準備する必要があります。なぜなら、都内区市町村の入札参加資格の取得手続きは、e-Tokyoを利用した電子申請となっており、この電子申請を行うには、「電子証明書尾+ICカードリーダ」を用意し、システムにログインをしなければならないからです。
「電子証明書+ICカードリーダ」は、電子入札コアシステム対応の民間認証局から購入する必要があります。代表的な民間認証局として、以下の5つがあります。
| 認証局名 | サービス名 | ||
|---|---|---|---|
| NTTビジネスソリューション(株) | e-ProbatioPS2 | ||
| 三菱電機インフォメーションネットワーク(株) | DIACERT-PLUSサービス | ||
| (株)帝国データバンク | TDB電子認証サービスTypeA | ||
| (株)トインクス | TOiNX電子入札対応認証サービス | ||
| 日本電子認証(株) | AOSignサービス |
電子証明書もICカードリーダも、電子入札のために御社の備品として購入して頂くものになります。例えば、ビックカメラやドン・キホーテなどでPCの付属品として購入できるようなものではありません。
購入費用(本体価格)については、民間認証局ごとによって異なりますので、事前に確認をしておくとよいでしょう。また、民間認証局によって異なりますが、電子証明書+ICカードリーダは、申込をしてから発行まで、1週間程度かかるようです。
なお、弊所にご依頼頂くことによって、日本電子認証(株)の提供するAosignカードを特別価格でご購入いただくことができます。また、通常1週間程度かかる電子証明書の発行期間も、2~3日程度に短縮して発行してもらうことも可能です。
どの民間認証局から電子証明書およびICカードリーダを購入すればよいかわからないといった方は、ぜひ、ご相談いただければと思います。
![]()
2.パソコンの入札環境設定のための手続き
購入した電子証明書やICカードリーダを、御社のパソコンで利用できるようにするための、パソコンの設定手続きが必要です。
このパソコンの設定手続きについては、購入元である民間認証局が発行しているマニュアルや「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス(e-Tokyo)」のホームページに掲載されている設定手順をよく見ながら作業する必要があります。
なお、これらの手続きをすべて行ったうえで「動作確認」を行い、パソコンの環境設定が整ってからでないと「3.e-Tokyoを利用した電子申請の手続き」に進むことができません。
- ログイン画面が出てこない
- PIN番号を入力しても操作を先に進めることができない
といったケースでは、パソコンの環境設定にエラーが生じている可能性があります。
![]()
3.e-Tokyoを利用した電子申請の手続き
「1.電子証明書やICカードリーダを購入し」「2.パソコンの環境設定」が終わって、はじめて「3.東京電子自治体共同運営 電子調達サービス(e-Tokyo)」を利用して、各市区町村の入札参加資格を申請できるようになります。
東京都内区市町村の入札参加資格の申請は、電子申請ですので、「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス(e-Tokyo)」のホームページからアプリをダウンロードし、必要事項を入力のうえ、電子送信するという流れになります。
入力すべき必要項目としては
- 営業種目・取扱品目の選択
- 営業種目・取扱品目ごとの売上高の割り振り
- 営業種目・取扱品目ごとの過去3年間の契約実績
- 流動資産・流動負債・純資産・資本金などの財務状況
- 法人事業税・法人税・消費税の納税状況
- 従業員の人数
- 社会保険の加入状況
- ISOの登録状況
など、多岐にわたります。上記の必要項目の入力にエラーがある場合には、電子申請ができないことがあります。
![]()
4.申請窓口への書類の郵送
「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス(e-Tokyo)」を利用して上記の電子申請が終わった後、指定の受付窓口に書類を郵送する必要があります。必要書類の種類については、のちほど詳しく記載します。
受付窓口として指定される区役所・市役所は、あくまでもコンピューターによって選ばれた任意の窓口です。仮に御社が新宿区内にあったからと言って受付窓口が新宿区役所になるわけではありません。
![]()
5.承認・否承認の確認
書類発送後、1週間程度で、承認・否承認の通知がメールにて届きます。承認の場合は、「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス(e-Tokyo)」のホームページから受付票がプリントアウトできるようになります。
この受付票は、何回でもプリントアウトすることができますが、入札参加資格を取得していることを証明するものですので、指定の箇所に実印を押印し、裏面に「印鑑証明書」を添付して保管しておく必要があります。
仮に、否承認になった場合には、否承認の理由を確認し、補正・訂正のうえ、再度「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス(e-Tokyo)」から申請を行わなければなりません。
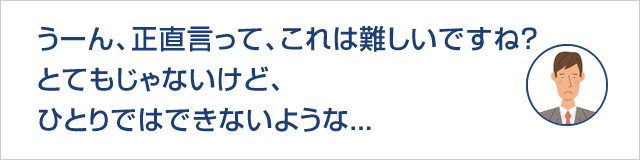
東京都内区市町村:入札資格を取得するための必要書類
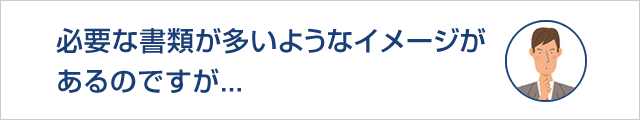
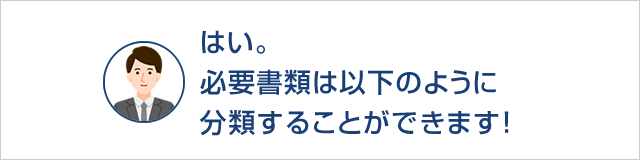
東京都内区市町村の入札参加資格を取得するには、「電子証明書やICカードリーダ」を取得のうえ、「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス(e-Tokyo)」を利用し得て電子申請することが必要でした。
もっとも「電子証明書やICカードリーダ」を購入するには、いくつもの書類が必要です。
また、「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス(e-Tokyo)」を利用して電子申請をしたあとも、受付窓口に書類の郵送が必要です。
そこで、ここでは、手続き全般を通して必要になる書類の種類について、まとめてご説明させて頂きます。
電子証明書・ICカードリーダ取得のための必要書類
「電子証明書やICカードリーダ」を購入するには、以下の書類が必要になります。
- 代表取締役の住民票
- 代表取締役個人の印鑑証明書
- 会社の印鑑証明書
- 会社の履歴事項全部証明書
- 電子証明書発行申込書
- ICカードリーダ購入申込書
手続きの流れの部分でも記載しましたが、東京都内区市町村の入札参加資格を取得するには、「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス(e-Tokyo)」を利用することが必要で、「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス(e-Tokyo)」を利用するには、民間認証局から電子証明書とICカードリーダの購入が必要です。
そして民間認証局から「電子証明書やICカードリーダ」を購入するには、代表取締役の住民票などの法定書類が必要です。
これは、電子証明書が「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス(e-Tokyo)」を利用うえでの、インターネット上の会社の身分証明書となるためです。電子証明書には、会社商号はもちろんのこと、会社の所在地や代表取締役の氏名といった重要事項がデータとして格納されるため、もろもろの法定書類が必要になります。
急いで東京都内区市町村の入札参加資格を取得したいといった場合には、代表取締役の住民票や印鑑証明書などは、あらかじめ準備しておくとよいでしょう。
都内区市町村の入札参加資格を取得するための必要書類
続いて、「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス(e-Tokyo)」を利用して電子申請をしたあとに、受付窓口に郵送が必要となる書類は、以下の通りです。
- 直前決算の財務諸表である貸借対照表、損益計算書
- 法人事業税納税証明書
- 法人税納税証明書
- 消費税納税証明書
- 履歴事項全部証明書
注意して頂きたいのが、税金の未納です。税金に未納があっても納税証明書は取得することができますが、未納があると「東京都内区市町村の入札参加資格」を取得することができません。
入札に関する費用は税金で賄われているのですから、税金に未納がある会社が入札参加資格を取得できないのは当たり前ですね。
時折、散見されますが、入札にチャレンジする以上、税金の未納がないようにくれぐれも注意をしていただければと思います。
なお、弊所に入札参加資格の取得手続きの代行をご依頼頂いた際には、納税証明書はすべて弊所にて代理取得することが可能ですので、ご安心ください。
行政書士法人スマートサイドに依頼する6つのメリット
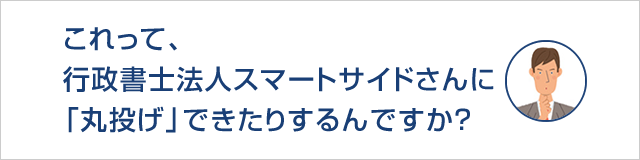
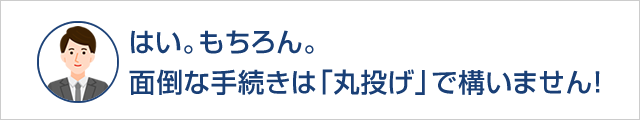
以上、手続きの流れや、必要書類について見てきましたが、如何でしょうか?自分にもできそうですか?それとも、自分ひとりの力では無理そうですか?
とくに
- パソコンの設定が苦手な方
- 急いで区市町村の入札に参加したい方
- 本業が忙しく、手続きに時間を割いている暇のない方
にとっては、自分で行うのは難しそうです。そういった場合には、行政書士法人スマートサイドが御社の入札参加資格の取得をサポートさせて頂きます。
以下では、弊所に「都内区市町村」の入札参加資格申請をご依頼頂くメリットについて、解説させて頂きます。
メリット1:電子証明書の購入申込・受取も代行
すでに記載しているように「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス(e-Tokyo)」を利用するには、電子入札コアシステム対応の民間認証局から「電子証明書」と「ICカードリーダ」を購入しなければなりません。
量販店やネットで購入できるものではなく、購入申込書のほか代表者の住民票などの法定書類も必要です。また、電子証明書は本人限定受取郵便で届くため郵便局まで受け取りにいかなかければならないという手間も発生します。
弊所にご依頼頂いた際には、電子証明書+ICカードリーダの購入申込、受取を代行させて頂きます。
メリット2:電子証明書購入費用の割引サービスあり
弊所では、日本電子認証(株)のAosignカードをお勧めしています。行政書士紹介割引を利用することによって、通常価格より最大2万円程度、電子証明書を安く購入することができます。
また弊所にご依頼頂くことによって、すぐに日本電子認証(株)に申込手続きを行いますので、通常1週間程度かかる電子証明書の発行期間を2~3日、短縮することが可能です。
メリット3:パソコンの訪問設定も対応可
皆さんの中には「パソコンの設定がどうしても苦手」という方もいらっしゃるのではないでしょうか?「手続きの流れ」の中のでも、説明しましたが「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス(e-Tokyo)」を利用して「東京都内区市町村の入札参加資格」を取得するには、
- 御社PCで電子証明書を利用できるようにする設定
- e-Tokyoを利用できるようにする環境設定
- e-Tokyoにログイン後の電子証明書の登録
といったパソコンでの作業が必要になります。
弊所にご依頼頂いた際には、実際に御社に訪問し、上記のようなパソコンの設定を行います(東京都内に限る)。これにより、すぐに入札に参加できる状態が整うことになります。
メリット4:納税証明書などの必要書類も代理取得
東京都内区市町村の入札参加資格を取得するには
- 履歴事項全部証明書
- 法人事業税納税証明書
- 法人税納税証明書
- 消費税納税証明書
といった各種法定書類が必要になります。実際に、これらの書類を取得するとなると「法務局」「都税事務所」「税務署」に足を運ぶことになり面倒ですね。
弊所にご依頼頂いた際には、上記4つの書類のすべてを、御社に代わって代理取得させて頂きます。
メリット5:入力申請は弊所のパソコンから
「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス(e-Tokyo)」を利用した電子申請は、「御社のパソコン」からではなく「弊所のパソコン」から行うことが可能です。
必要事項の入力および、電子送信、その後の受付状況の確認に至るまで、全て、弊所のパソコンから行うことができます。
メリット6:申請から承認までスケジュール管理
申請後は、1週間程度で、承認・否承認の通知が届きます。否承認となった場合には、なぜ否承認になったかの理由を確認し、再度申請することが必要です。
弊所では、申請後の「承認・否承認の通知の確認」はもちろんのこと、「受付票のプリントアウト」「資格適用日の確認」に至るまで、御社が実際に「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス(e-Tokyo)」の入札資格者名簿に掲載されるまでのスケジュール管理を行うことが可能です。
東京都内区市町村:入札資格取得のための期間と費用
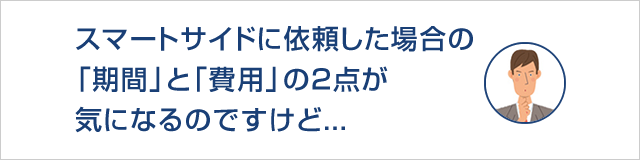
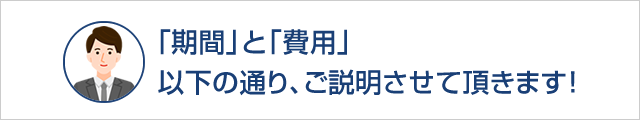
東京都内23区市町村の入札参加資格取得手続きを、行政書士法人スマートサイドにご依頼頂いた場合の
- 入札参加資格取得までの「期間」
- 手続きの代行に係る「費用」
については、大変多くのお客様から質問される事項です。そこで、以下では、お客様のもっとも気にされる「期間」と「費用」について、ご説明させて頂きます。
入札参加資格を取得するまでの期間
| 手続き | 期間 |
|---|---|
| お問合せ~初回打ち合わせまで | 1週間程度 |
| お申込み~電子証明書の取得まで | 1週間から10日程度 |
| 電子証明書の取得~申請完了まで | 1週間程度 |
| 申請完了~承認通知の受領まで | 1週間程度 |
上記の期間は、あくまでも標準的な処理期間を記載しています。例えば、どうしても急ぎで区市町村の入札に参加したいといた場合には、お問合せの翌日に打ち合わせを実施させて頂くことも可能です。
また、急ぎ対応が必要なケースでは、電子証明書の取得にかかる期間を2~3日まで短縮することも可能です。
通常は、お問合せ頂いてから申請完了まで3週間から1か月程度の期間を見て頂いておりますが、急ぎ対応については、状況に合わせて柔軟に対応させて頂きますの、個別にご相談下さい。
入札参加資格を取得するまでの費用
事前相談料
|
事前相談料(要予約) 手続きに関する事前相談をご希望の方のために「弊所にて」「1時間程度」「有料の事前相談」を承っております。 |
¥11、000
|
|---|
東京都内区市町村の入札参加資格の申請費用
| ①電子証明書・ICカードリーダの取得 | ¥55、000 |
|---|---|
| ②パソコンの設定(1台) | ¥33、000 |
| ③都内区市町村への入札参加資格申請
(申請業種が1~4業種までの場合) |
¥110、000 |
| ①~③行政書士報酬として(小計) | ¥198、000 |
| ④履歴事項全部証明書(2通) | ¥4、400 |
| ⑤納税証明書(3種類) | ¥6、600 |
| ①~⑤御社負担分として(合計) | ¥209、000 |
申請する営業種目数に応じた価格表
「③都内区市町村への入札参加資格申請」の費用について。東京都内区市町村の場合、全部で10の営業種目で入札資格を取得することが可能です。申請する営業種目の数によって、営業種目ごとの売上高の割り振りが必要になるなど、作業量が異なります。そのため、弊所では、申請する営業種目ごとに、価格を設定しています。
申請業種が1~4業種の場合は、110、000円(税込み)です。申請業種が5~7の場合は143、000円、申請が業種が8~10の場合は176、000円になります。
| 申請業種が1~4業種の場合 | ¥110、000 |
|---|---|
| 申請業種が5~7業種の場合 | ¥143、000 |
| 申請業種が8~10業種の場合 | ¥176、000 |
なお、申請先自治体の数によって、費用が変動することはありません。例えば、杉並区1か所に申請する場合と、東京都内区市町村全59の自治体すべてに申請する場合とで、費用に変わりありません。
東京都内区市町村:入札資格取得の成功事例のご紹介
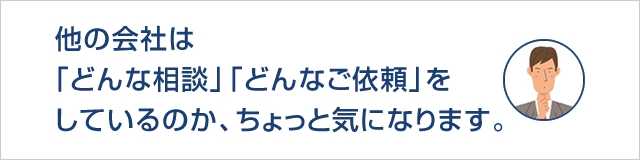
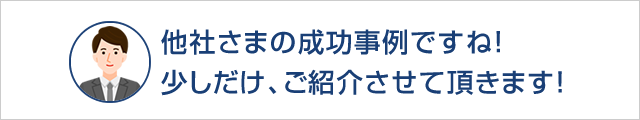
弊所にご依頼頂いた他社の申請実績については、御社の参考になるかもしれません。似たような状況にある会社がいかにして入札参加資格を取得したことが分かれば、参考にすることができます。
そこで以下では、実際に弊所サービスをご利用いただいたお客様の事例をご紹介させて頂きます。
墨田区:運送業のお客様
ご相談内容
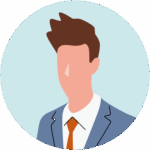
長引くコロナの影響で売上が厳しくなってきてしまった。まえから公共事業には興味があったので、これを機に、地元の墨田区をはじめとした区市町村の入札参加資格を取得して、営業範囲を民間だけでなく、役所にも広げていきたい。
弊所のサポート内容
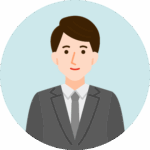
「コロナの影響を受けていない業種はない」と言ってもいいくらい、ほとんどすべての業種でコロナによって売上が減少してしまっていますんね。
そんな中、営業範囲を民間だけでなく、役所にも広げていきたいということで、弊所にご依頼を頂きました。電子証明書の取得・PCの設定・電子申請・必要書類の郵送とすべての手続きを弊所で代行することにより、無事、全59自治体の入札参加資格を取得することができました。
小平市:清掃業・廃棄物処理業のお客様
ご相談内容
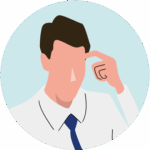
今まで都内区市町村の入札資格を持っていましたが、担当していた社員が引継ぎを行わないまま退職してしまったため、手続きの仕方が誰もわからなくなってしましました。どうしても自分でやる時間がないため、手続きを外注したいと思います。
弊所のサポート内容
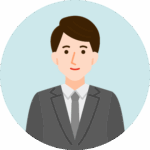
「担当社員の退社に伴って、社内に分かる人が誰もいなくなってしまった」ということは本当によくあることです。単なる退社であれば、まだ準備ができたかもしれませんが、突然の不幸や喧嘩別れの場合には、引継ぎがうまく行かないこともありえます。
この会社の状況をお調べしたところ、すでに区や市の入札参加資格の有効期限が切れている状況でしたので、早急に入札参加資格を取得しなおしました。
港区:IT関連・情報処理業のお客様
ご相談内容
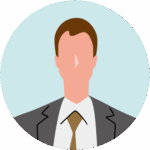
取引先の会社から、突然「e-Tokyoの入札参加資格を持ってほしい」と催促されまして。今まで入札とは縁がなかったですし、突然「e-Tokyo」と言われても、何のことかわからず、ネットを検索していたら、スマートサイドのホームページにたどりついた次第です。
弊所のサポート内容
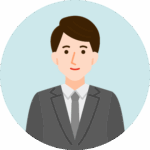
「取引先や関連会社から入札資格を持ってほしい」と催促されたという話は、よく聞きます。このお客様の場合、事情はともあれ、「急ぎの対応」が必要だったので、まずは、早急に「電子証明書の取得手続き」から開始することになりました。
タイミングも良かったこともあり、お問合せの3週間後には、東京都内区市町村全59の自治体すべての入札に参加できるようになりました。
その他の相談事例
| 業種 | 精密機械・産業用機器の製造および販売 |
|---|---|
| 役職等 | 代表取締役(40代・男性) |
| 相談内容 | 急ぎでお願いした場合、最短いつから東京都の入札に参加することができますか? |
| 業種 | IT関連・情報書類業務 |
|---|---|
| 役職等 | 営業部長兼エリアマネージャー(50代・男性) |
| 相談内容 | 東京都入札参加資格申請を依頼した場合の、流れと費用を教えてください。 |
| 業種 | 衣料品の製造、販売、加工業 |
|---|---|
| 役職等 | 代表取締役(60代・男性) |
| 相談内容 | 東京都、都内区市町村、全省庁の入札資格をすべて、依頼できますか? |
| 業種 | イベント・パーティーの企画運営 |
|---|---|
| 役職等 | 総務部長兼常務取締役(50代・男性) |
| 相談内容 | 東京都と区市町村の両方の入札資格を同時に取得することはできますか? |
東京都内区市町村の入札に参加したいとお考えの方へ
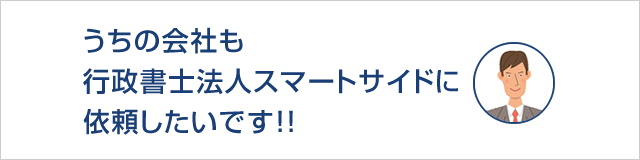
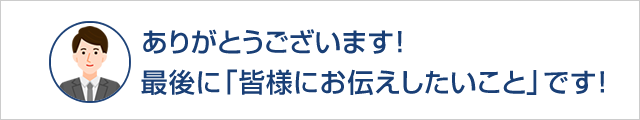
最後までお読みいただきありがとうございます。
- 東京電子自治体共同運営 電子調達サービス(e-Tokyo)
- 東京都内区市町村の入札参加資格の取得手続き
について、ご理解いただけましたでしょうか?
インターネット上を検索すると、さまざまな情報に触れることができると思いますが、「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス(e-Tokyo)「東京都内区市町村の入札参加資格の取得手続き」について、ここまで詳しく書いているページは、なかなかないのではないでしょうか?
さて、ここで私から皆さんへのメッセージです。それは、皆さんの目的は何ですか?という質問です。
皆さんの目的は
- 入札参加資格を取得すること
- 手続きを自分一人の力でやり遂げること
- 時間がかかっても良いから申請を自分で行うこと
- 労力を顧みず、頑張って入札参加資格を申請すること
なのでしょうか?中には、どうしても自分一人の力で手続きを完了させたいという方もいるかもしれません。
しかし、みなさんの本当の目的は、「案件を落札して公共の仕事を受注し、売上アップに貢献すること」にあるのではなのではないでしょうか?
考えてもみてください。入札は、同業他社との競争です。少しでも経験を積み、より多く入札案件を落札している会社が有利なのは当たり前です。
皆さんが、手続きについて勉強したり、悩んだり、どうしようか考えているうちに、皆さんの競合はどんどん先に進んでいってしまいます。入札参加資格の取得で立ち止まっている場合ではありません。
入札参加資格の申請は、役所の仕事を落札する上での事前準備段階です。その事前準備段階で、労力を使い果たし、時間をかけている場合ではありません。入札参加資格の取得はとっとと終わらせて、少しでも早く入札に参加すべきなのです。
であれば、皆さんのやることはもうお分かりですね。皆さんは皆さんにしかできない仕事(本業)に専念し、手続きは、外部の専門家に外注するのが、費用対効果のうえで、一番賢い選択といえるのではないでしょうか?
ここまでお読みいただいてお分かりの通り、行政書士法人スマートサイドは、「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス(e-Tokyo)「東京都内区市町村の入札参加資格の取得手続き」の専門家です。皆さんが苦手とするパソコンの環境設定や書類の取得を代行し、スピード感を持って、入札参加資格の申請を行うことができます。
「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス(e-Tokyo)「東京都内区市町村の入札参加資格の取得手続き」でお困りの際には、ぜひ、下記問い合わせフォームからご依頼頂ければと思います。